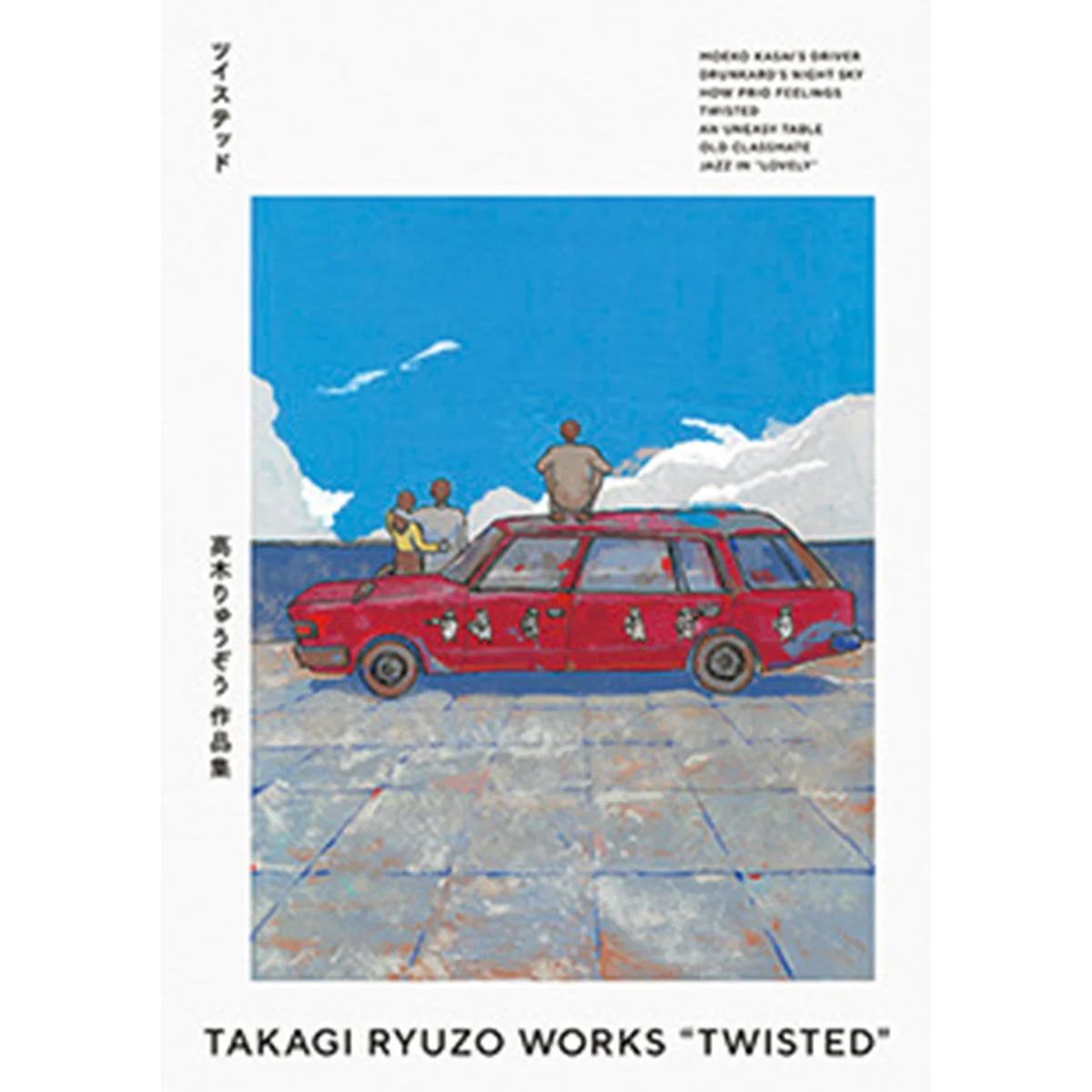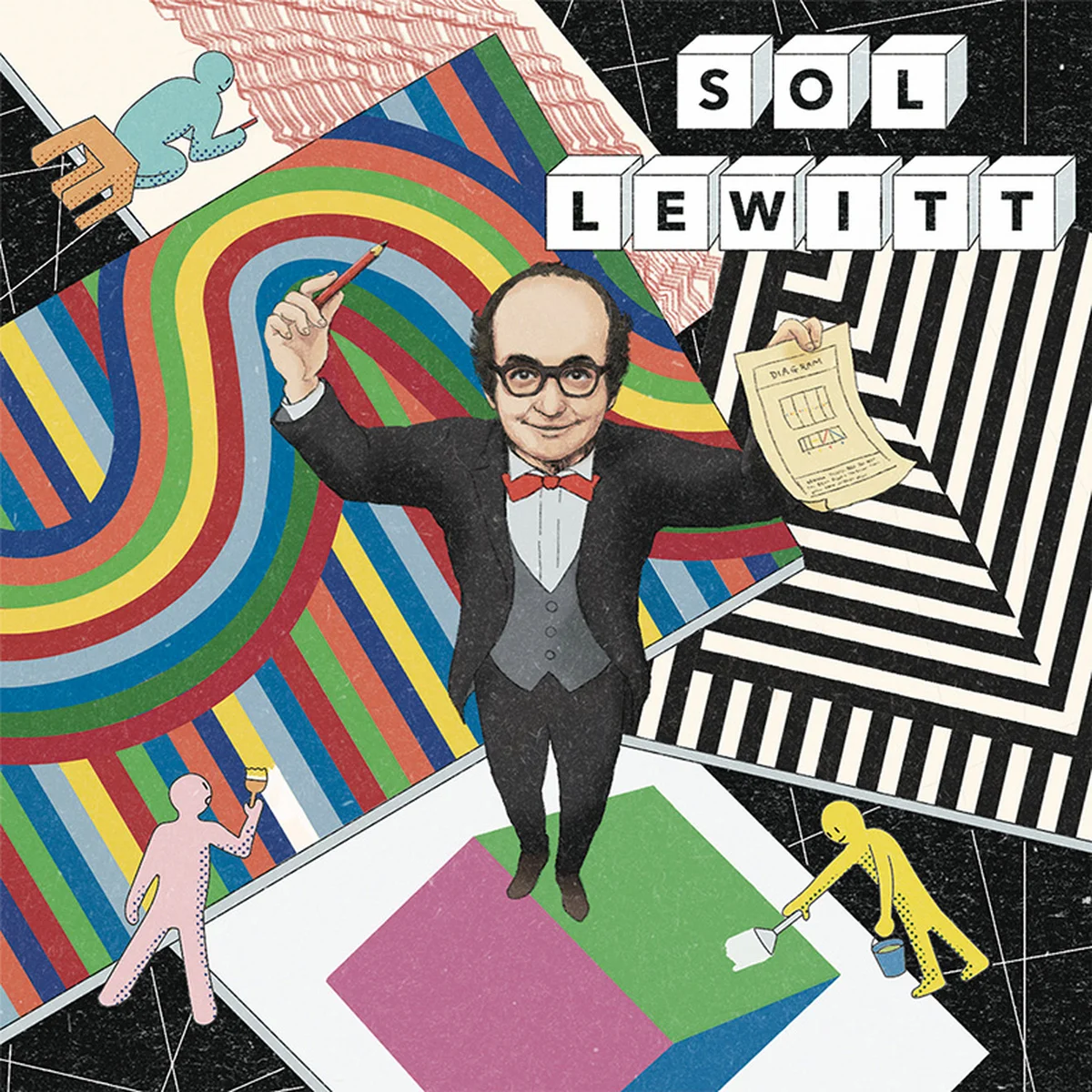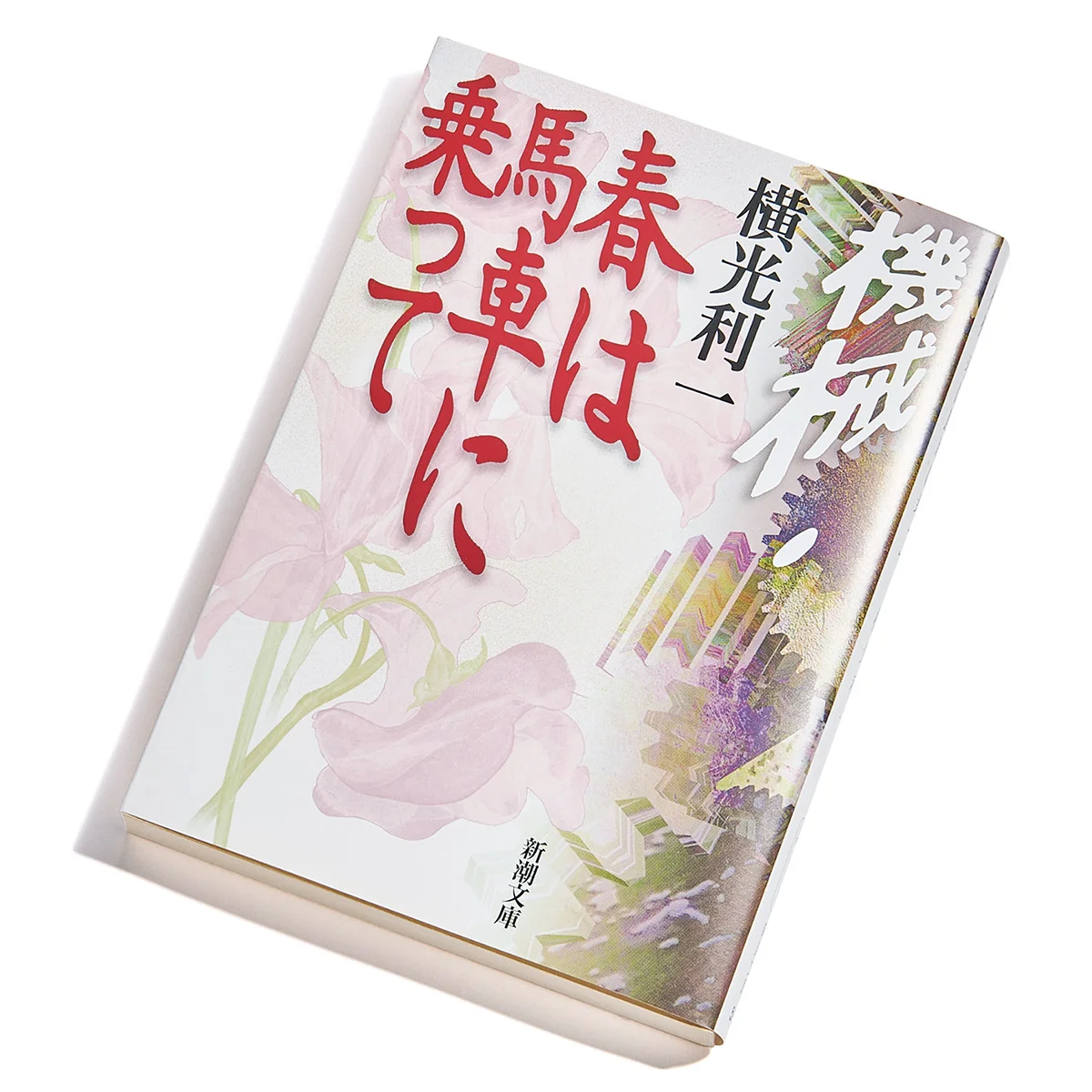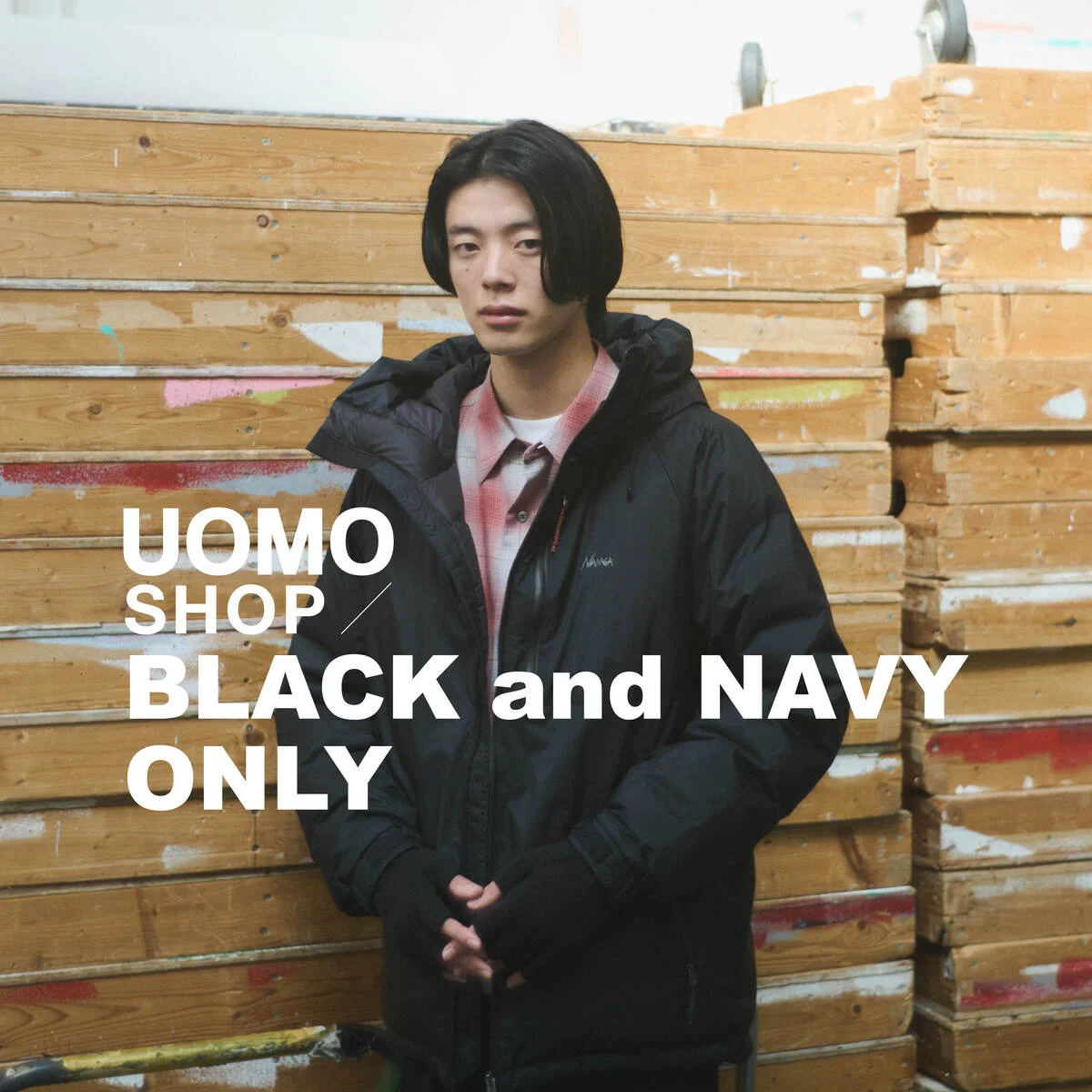第16回|睡眠を哲学する。眠ること自体の魅力って何?

ローマで生まれ育つ。ピュージェットサウンド大学所属。著書『The Philosophy of Envy』で知られる。今回の内容は「The Value of Sleeping」という論文に基づく。個人的には眠りの儀式的価値を面白く感じた。アロマやアイマスク、枕など睡眠関係のグッズが膨大にあり、モーニングルーティン動画が人気なのは、この価値に人々が注目している表れだろう。
誰も眠りから縁を切ることはできない。そのためか、睡眠学者の柳沢正史がメディア出演で提示する助言は、多くの注目を集める。柳沢曰く、現代人は睡眠時間が慢性的に不足しており、寝すぎは病気でない限りありえない。この知見を活用すれば、睡眠の質を上げ、覚醒時のパフォーマンスを上げられる。
しかし、これは覚醒のために眠りを評価する発想であって、ここには眠りそのものの価値を考える視点がない。そう言われてもピンとこないかもしれないが、「健康リスク抜きに眠らずにいられる錠剤があるとしても、それでも眠るべきだとすればなぜか」と問いかけたときの答えがそれに相当すると思えばいい。何かのためではなく、眠ること自体の魅力とは何だろうか。
サラ・プロタシは、それを、①眠り儀式、②共寝、③覚醒からの退却、④人間性の表現としての眠り、この4つの観点から説明している。これらを順に見ていくことで、誰もが日々生きている眠りの時間がもつ美的価値について考えることにしよう。
①パジャマに着替え、歯磨きをし、ベッドを整えて眠る。目覚ましを止めて布団を整え、歯を磨いて、コーヒーをいれる。これらの「儀式」の価値は、生活テンポを減速させ、静かで落ち着いた楽しみを感じさせるところにある。この落ち着きのおかげで、日常の豊かな美的側面を味わうことができる。
②歴史を振り返ると、どの文化でも共食と同じくらい共寝を大事にしていることに気づく。共寝をすると、ベッドを共にする仲間に接触しうる範囲に自分の身を置くことになる。誰かに身体を添わせるように眠ることには、精神的かつ感覚的な親密性が宿っており、その身体的経験に価値があるのだ。
③眠りの最中、人はほぼ意識のない状態になる。それを現実からの避難所だと考えられるかもしれない。「過酷な現実から退却する」ことは、現実で感じる疲労や不安などへの感情的な癒やしになっている。家事や仕事で忙しい人にはピンとくるかもしれない。
④はいくらか抽象的な価値だ。どんなに屈強で権力があり、資産や仲間がいても、眠っているときは無防備で弱い。ある意味で、眠りは、人間がもつ本質的な無防備さをあらわにしていると言える。何で取りつくろっても、その点は変わらない。この拭いがたい弱さは、「ヴァルネラビリティ」と呼ばれる。ヴァルネラビリティを反復的に表現する眠りという活動を、プロタシは人間本性の一種の表れとして解釈し、そこに価値を認めている。今夜眠るとき、何かのためではない眠りの価値を考えてみてほしい。
哲学者。京都市立芸術大学美術学部デザイン科で講師を務める。著書に『増補改訂版 スマホ時代の哲学』『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』『鶴見俊輔の言葉と倫理』など。