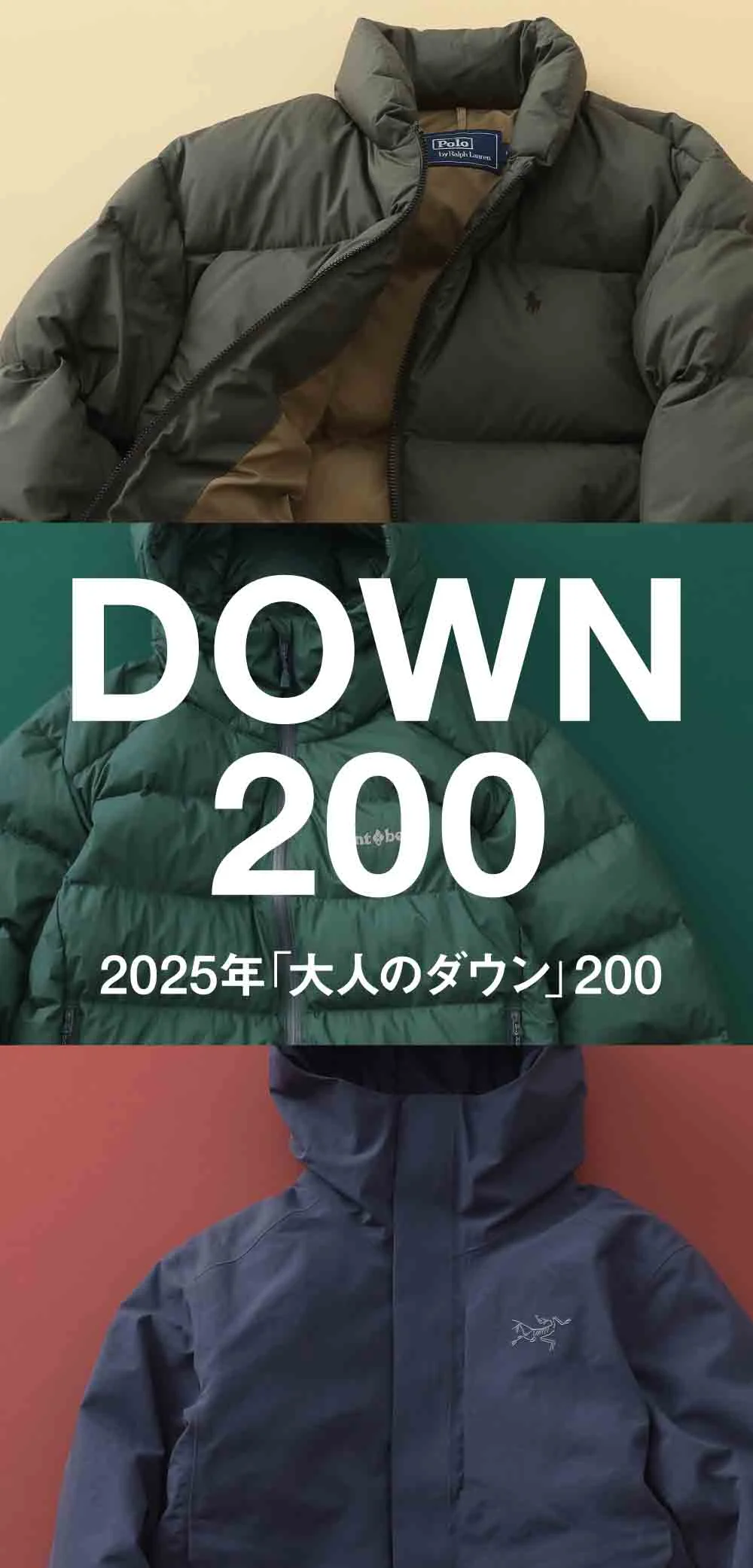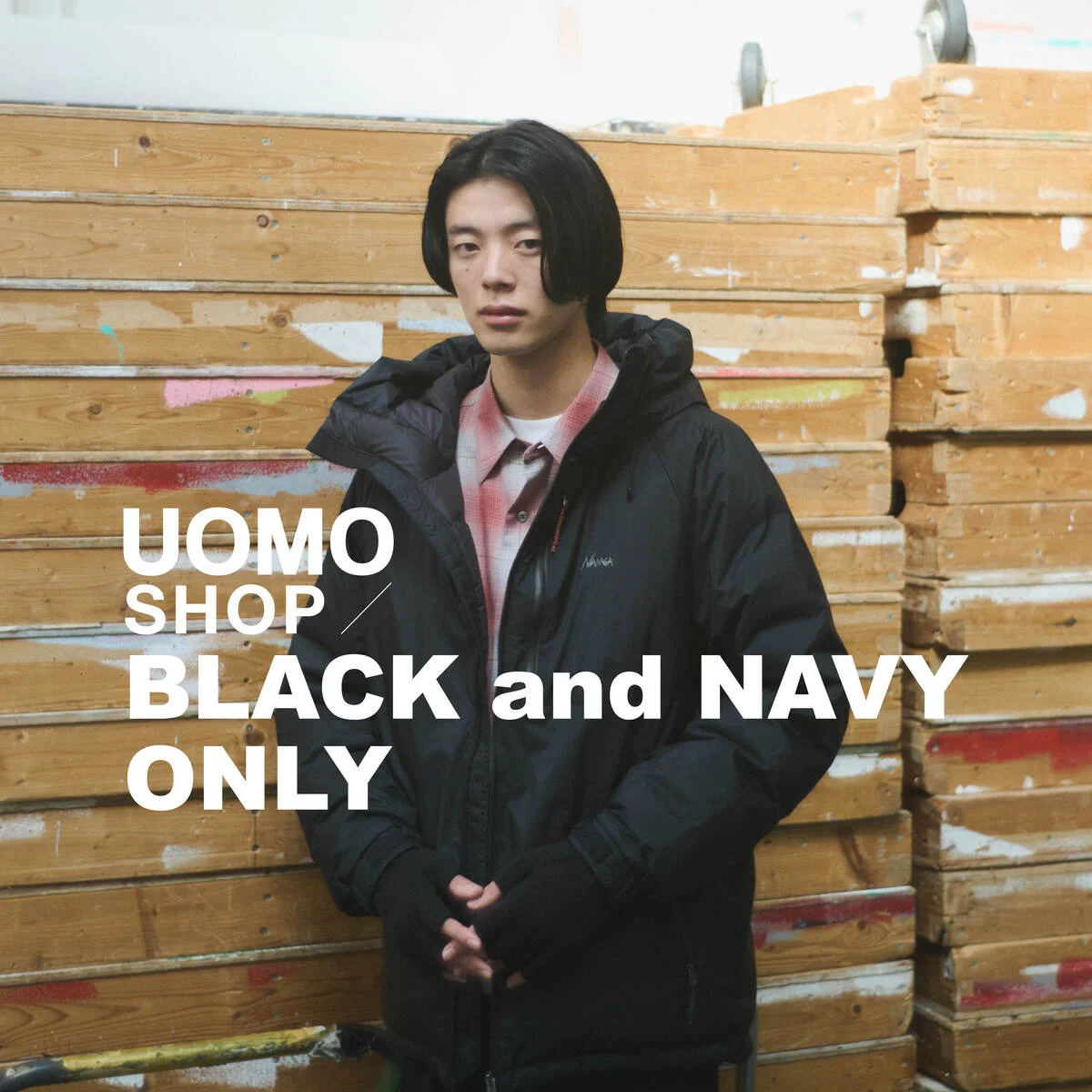かつて小木“POGGY”基史さんは、海外とのネットワークを深めることで、新しいラグジュアリーとストリートの世界を自らのスタイルで表現してきた。でも、彼が今気になるのは日本人ならではのものづくり。そこには海外が憧れる日本の職人的な精神性やクリエイティブが詰まっていることを伝えたいという。今回はその一環として、彫刻家・流政之氏のスタジオを訪ねてみた。

ユナイテッドアローズから独立後、ファッションキュレーターとして活躍。自身のコレクションやスタイルを収めた『Poggy Style: Dressing for Work and Play』がリッツォーリ社より発売中。
流政之の彫刻は、強く重い
香川に集まるアーティストの存在に興味をもったPOGGYさんは、その中でも国際的に活躍した彫刻家、流政之氏の作品に共鳴した。世界が日本に求める、繊細さとダイナミックさが共存している。

日本人のアイデンティティに
新しいラグジュアリーがある
ファッションキュレーターのPOGGYさんは、海外とのネットワークを駆使して世界中のいいものを日本に紹介し続けてきた。しかし海外は、日本のファッションやヴィンテージ、ものづくりを高く評価しているにもかかわらず、日本人自身がその価値に気づいていないという。「だから今は日本のよさを再評価し、発信したい」と語る。
「インポート主義の時代で育った僕は、バイヤーやディレクターの仕事を通して、海外の面白いブランドやお店を探し続けてきました。海外の人を日本でアテンドすることが多いのですが、彼らはいつも目を輝かせて楽しんでいます。サーフィンが好きな人がLAで暮らしたくなるように、ファッションが好きな人は日本のものづくりやクオリティに惚れ込んでいるんです」
POGGYさんは2年前、香川を訪れた際に石のことを学び、興味をもった中で、流政之の存在を知った。晩年まで制作していたスタジオは、現在予約制の美術館として公開されている。
「戦争の時代を生き抜いた流さんの経歴を知れば知るほど、作品の鋭さや強さを感じますね。ほかの日本の彫刻家とはどこか違う、アーティストとしての強さは、今、海外の人たちが求めている日本の魅力ともいえます。僕が考えるラグジュアリーとは、アイデンティティから出てくる“重み”。日本人が日本のブランドに、日本でものをつくることにもっと誇りをもってほしい。僕はそれをファッションの視点で世界だけでなく国内にも発信することで、新しいラグジュアリーの世界をつくれるんじゃないかと思っています」





館長の香美佐知子さんと
作品群を眺めながら
POGGY(以下、PGY):初めて来ましたが、すごくいい場所ですね。流さんはどうしてこの土地に辿り着いたんでしょうか?
香美:もともと流は長崎出身で、終戦の日本を見る旅の途中に寄ったこの地に制作の拠点を構えました。
PGY:ジョージ・ナカシマさんも、流さんが讃岐民具連を立ち上げたことをきっかけに香川に来たと聞いています。
香美:日本とアメリカを行き来していた流がニューヨークでジョージ・ナカシマと出会い、自宅の家具を作ってくれたことから関係が始まりました。流は民具連を1963年に発足していて、その翌年にナカシマを民具連に招き入れました。
PGY:イサムノグチさんも含め、香川県には海外からも評価の高いアーティストが多いイメージです。
香美:庵治は当時から石材のハブの機能をもつ地でした。採掘できるとはいえ、小木さんが気になっていらした赤御影や黒御影の石を日本で採掘できる場所は限られています。しかし世界の石材を入手できる土地だったこと、そして腕のいい職人たちがいたことで、流は庵治を拠点として選んだようです。
PGY:海外の人のほうが日本のことをよく知っている場合も多いですよね。ファッションは特にそうです。先ほどの庵治の石の話にも似ていますが、日本にはいろいろなジャンルのヴィンテージが集まっています。サンプルを買いに来たり、買い物を楽しむ海外の友人がとても多い。家具の世界も似ているのでは?と思っています。
香美:おっしゃるように、ミッドセンチュリーや民藝のようなものづくりを見せてくれるお店も増えましたね。
PGY:ヴィンテージの価値が高まったり、流さんのような重要人物が日本にたくさんいることを知ると、家具はすごく面白い世界だと思います。
香美:そうですね。芸術家同士が支え合うような民藝や民具連のように、ものづくりの世界でも積極的な連携があれば、現代にはまた違った世界が見られたかもしれません。
PGY:民藝のように相互扶助的な思想ではなかったのですね。一人一人がアーティストとして戦っていたシビアな世界だったわけですもんね。
香美:顧客の要望に対して何かを作るのがデザイナー。誰に認められなくても、自分の考える何かを作るのが芸術家。そこに違いがあると思っています。
PGY:ところで香美さんが好きな流さんの作品はいつの時代ですか?
香美:いずれの時代の作品も魅力があって難しいですね。ただ、しいて個人的に収集したい作品と聞かれれば、1950〜’60年代の石彫。ワレハダの技法を開眼された時代のそれは厳格で規則性があり、かっこいいです。
PGY:僕も、小さいですが2階の庭にあった刀のような作品が好きです。
香美:さすが、お目が高い。
PGY:ありがとうございます。