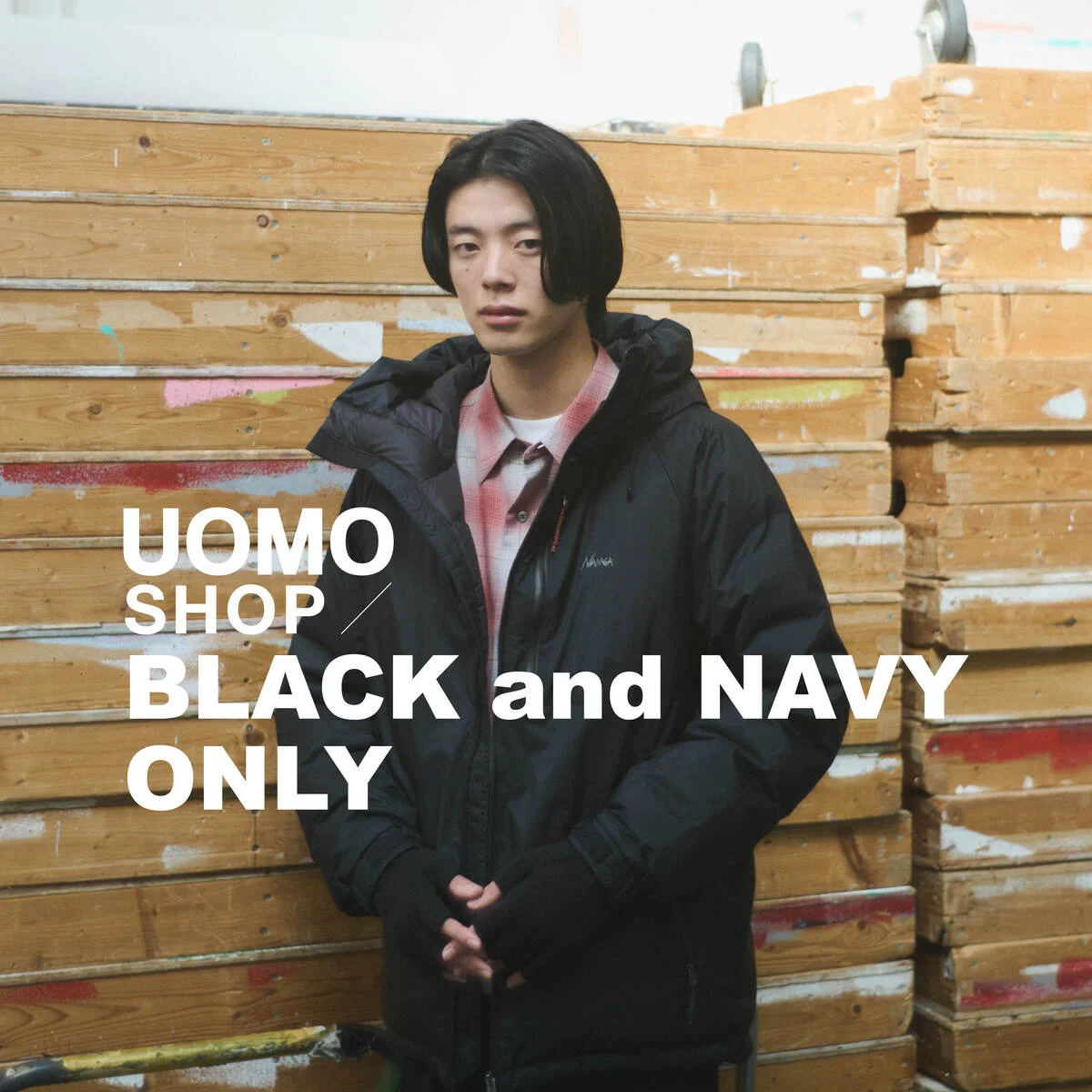博覧強記の料理人・稲田俊輔が、誰もが食べることができながら真の魅力に気づけていない、「どこにでもある美味」を語り尽くす。
第5回|冷やしたぬきを一心不乱にズビズバと啜り込む
「冷やしたぬきは無心の食べ物である」
これは、文筆家であり無類の麺好きとしても知られた僕が、今とっさにでっちあげた言葉です。しかしこれはなかなか芯を食った言葉なのではないかと、今ひとりで悦に入っています。
ざる蕎麦は、あんなに単純な食べ物なのに、意外と無心になれません。蕎麦を一度に手繰る量はどれくらいがいいのか。つゆはどれくらいつけるべきか。ネギとわさびはどのように運用すべきか。蕎麦には、茶道や華道などにもどこか似た「蕎麦道」のような世界があります。「てやんでい、蕎麦くらい好きに食わせろってンだ」と強がってはみても、心のどこかで蕎麦道の作法のようなものが気になってしまいます。
蕎麦はそもそもおいしい食べ物ですが、それが好きになりすぎてしまうと、ある時点から心の中に、何かと小うるさいジジイが住みつき始めてしまいます。その人格を僕は「小生」と呼んでいます。単に腹が減って、あるいはさっぱりしたものが食べたくてざる蕎麦を啜っているだけのはずなのに、心の中の小生は、「汁は小生好みであり、蕎麦も喉越しは悪くないが、時期のせいか香りは決して満足のいくものとは言えない」などとしゃしゃり出てきてケチをつけます。ちなみに小生に人格を完全に乗っ取られた中年男性は、そういうことをいちいちレビューサイトに書き付けるという、誰にも望まれていないボランティア活動に精を出したりし始めます。
温かいかけ蕎麦の場合は、あまり小生の出る幕はありませんが、じゃあ無心になれるかというとなかなかそうもいきません。その日は小寒かったから温かいものでも食べようと思っていただけのはずなのに、いざ天ぷら蕎麦なんかを目の前にすると、心は千々に乱れます。
千々に乱れた結果、やはりそこは天ぷら蕎麦を選択してしまいます。天ぷらそのものも魅力的ですが、そこから滲み出すかっぱえびせんの如き香ばしさを湛えた油がうっすら浮いた汁を、ジルジルと啜る誘惑から逃れ得る者はそうそうおりますまい。
しかしそこからが問題です。天ぷらは揚げたてのクリスピーさが少しでも残っているうちに食べた方が良いのか。いや、汁に浸ってふやけた天ぷらこそが天ぷら蕎麦の醍醐味であろう。しかしだからと言って、ふやかしすぎて海老とコロモが分離するまでに至るのはいかがなものか。そしてそうこうしているうちにも蕎麦は伸びていくばかりではないか。伸び切ってしまう前に蕎麦を先に啜り切ってしまうべきなのか。だがそれではその後に残されるものはコロモのはげた海老とコロモの残骸だけではないか。さすがに美しくない。やはり全てをバランスよく並行して食べ進めるべきであろう。伸びた蕎麦には伸びた蕎麦の良さというものだってあるではないか。
ようやくそこまで達観したのに、そこでいきなりまた小生が不意打ちのようにしゃしゃり出てきて、「蕎麦は喉越しが」とか「天ぷら蕎麦など邪道」などと余計なことを囁き始め、もうなんというか滅茶苦茶です。
冷やしたぬきに、そんな面倒は皆無です。
目の前に冷やしたぬきが降臨する。
底に溜まったつゆを持ち上げるように全体をかき混ぜる。
それを箸でガバッととらえ、ズビズバと啜り込む。
ズビズバと啜り込み、ズビズバと啜り込む。
たまに混ぜ損なったわさびのかたまりに当たって涙目になる。
しかしそれを抑え込むかのごとくまた次のひと口を頰張り、つゆの甘さに安らぐ。
さっきまでラーメンとどっちにするか迷っていたはずなのに、天かすとその油が染み出したつゆのコクは、ラーメンにも決して負けないコクの充足感をもたらしてくれる。
そうこうしているうちに、あっという間に最後のひと口だ。
食べ始めてから5分も経っていないのではないか。
あっけないものであるが、しかし我が冷やしたぬきに一片の悔い無し。
麺を啜り終えたつゆにはまだ天かすが点々と散らばっている。
もはや揚げ物としての出自を微塵も感じさせない、ふわふわの鰯雲のようだ。
なんだかやっぱり惜しい気がして、それを箸の先でかき集めて口中に放り込む。
いや、決して雲ではない。
ここまで身をやつしていても、これはやはり揚げ物である。
なんたる貴種流離譚。
まだわずかに残った天かすが余計に愛おしく、結局残ったつゆごとジルジルと吸い込んでしまう。
そこに紛れ込むネギや海苔の小片が、ありし日の思い出を、しみじみと語ってくれているようだ。
これが冷やしたぬきです。唇を油でヌメヌメと濡らしながら、無心で蕎麦を頰張り、名残惜しくつゆを啜る、そこに「小生」の出る幕はありません。逡巡も迷いも躊躇いもありません。あるものは心を満たす歓喜だけです。一心不乱。それが冷やしたぬきです。

料理人・文筆家。「エリックサウス」総料理長を務めながら、さまざまな食エッセイを執筆。近著に『食の本 ある料理人の読書録』(集英社)や『ベジ道楽』(西東社)などがある。