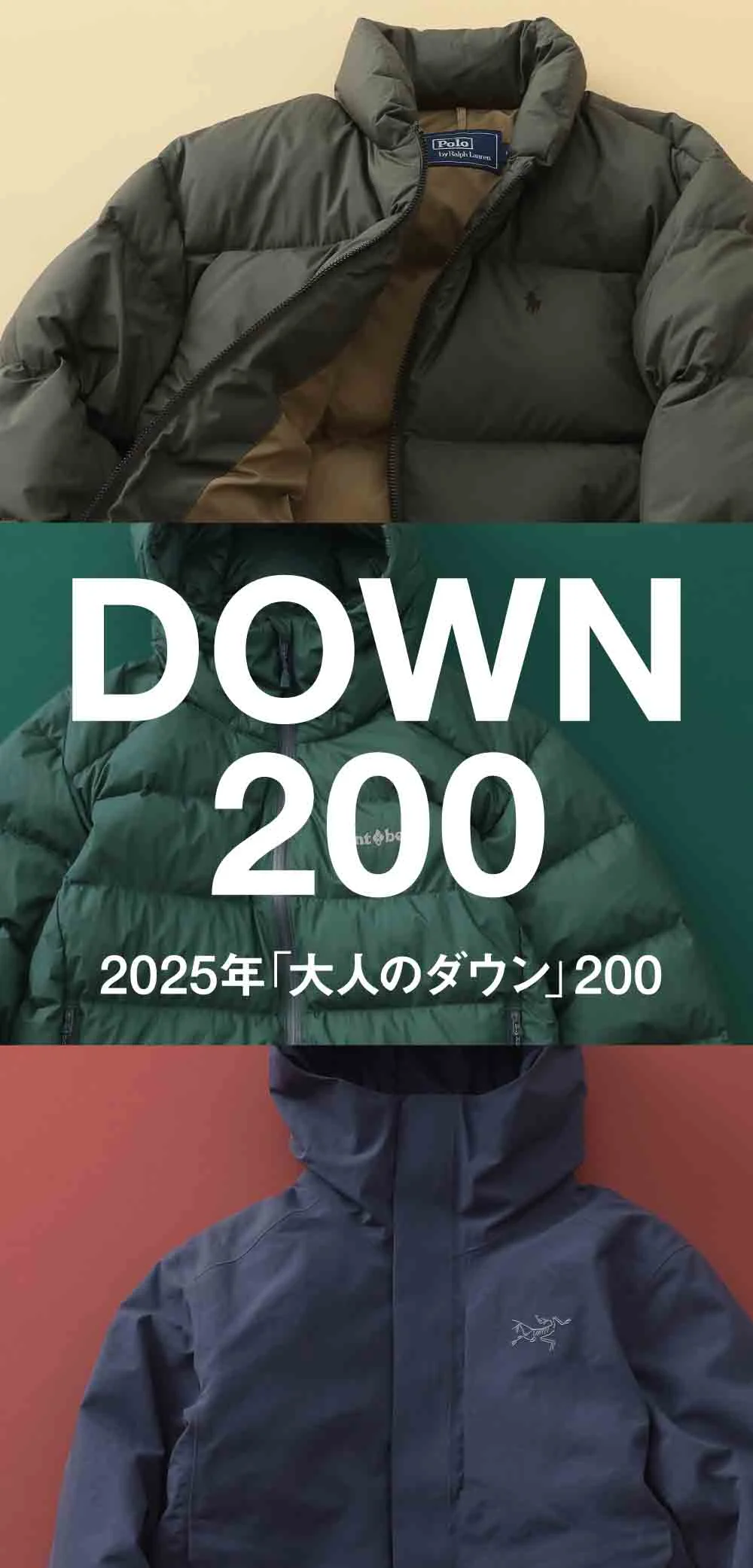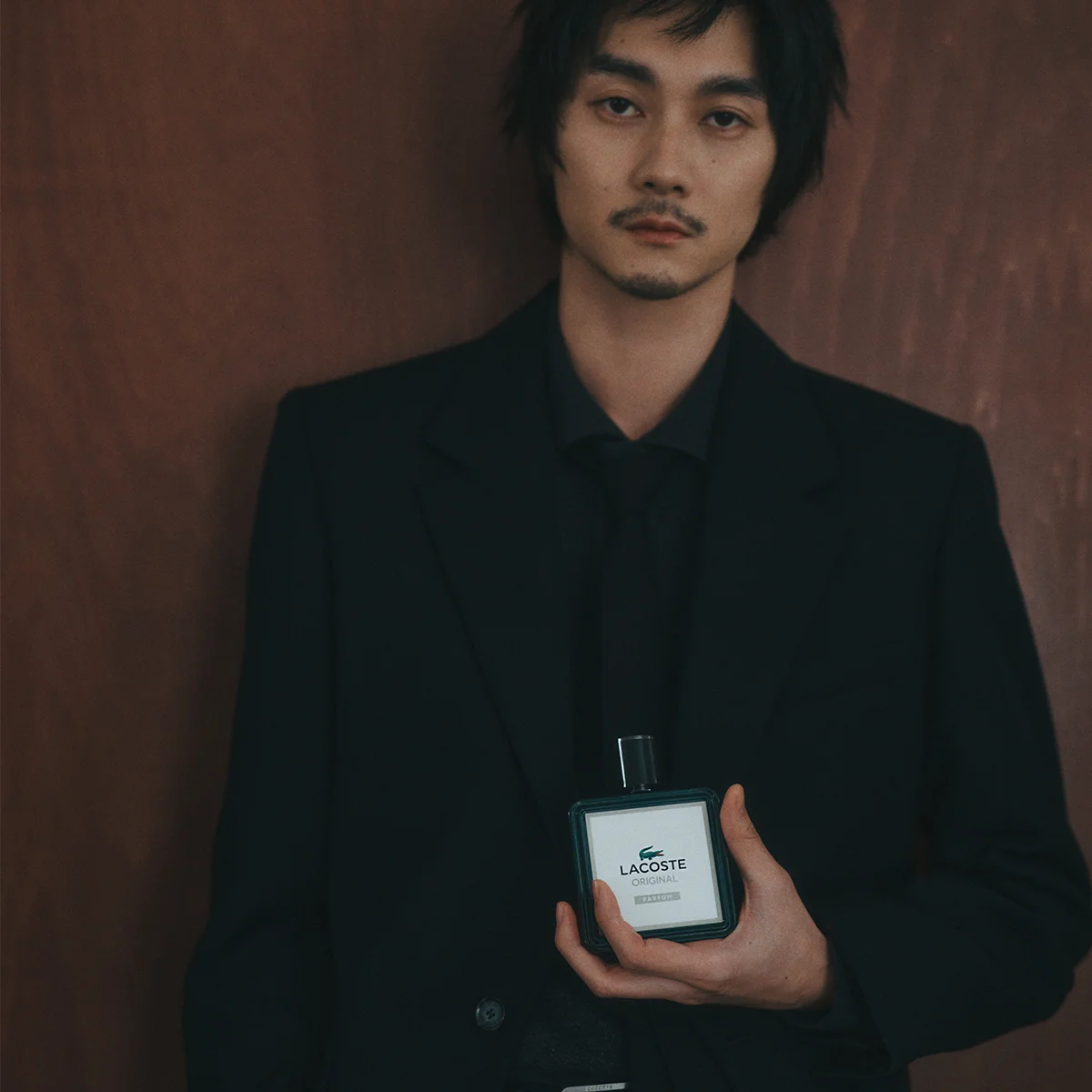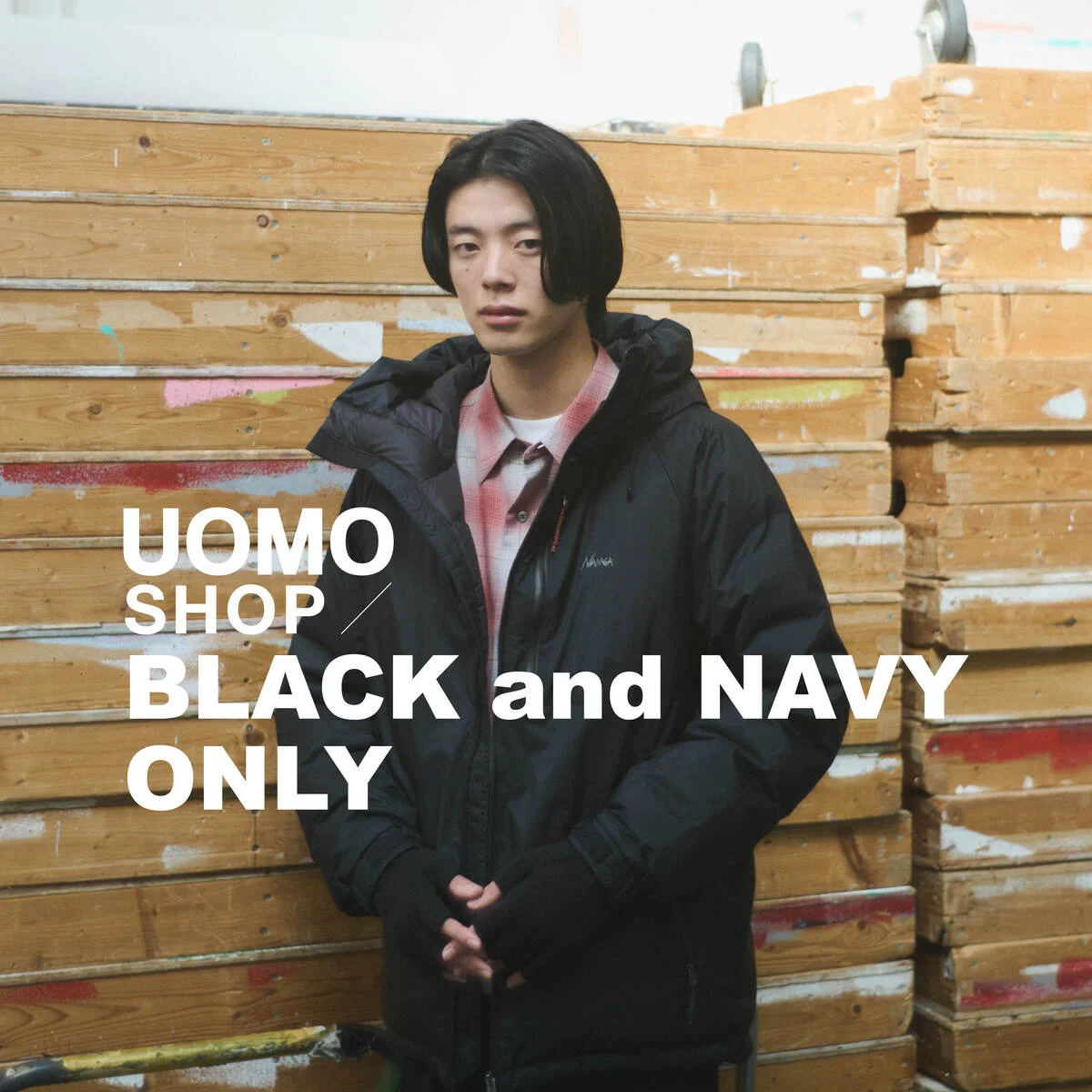第14回|AIは死者を甦らせることはできるのか?

紹介したのは、2025年に出たばかりの論文「Can Chatbots Preserve Our Relationships with the Dead?」(チャットボットは死者との関係をつないでいるか)。著者は、ベントレー大学のキャンベルとP・リュー、LMUミュンヘン大学のS・ナイホルムの3人。今回のテーマをもっと知るには、中島岳志編『RITA MAGAZINE 2 死者とテクノロジー』(ミシマ社)がおすすめ。
生前のログをもとに故人をAIとして復活させるサービスが国内外で複数始まっている。文字・音声・動画などのデータをもとに再現できるからだ。「いつもの歌が聴きたい」と言えばそれを歌い、「学校で悩みがある」と言えば故人が言いそうなことを言う。
企業は、AI化された故人が大切な人の死への慰めになると主張する。また、墓や遺言の準備などといった「終活」の一部として、故人の「思考の伝承」が可能になるという。
哲学者のスティーブン・キャンベルらは、「この種のサービスを利用すれば、故人との関係を継続していることになるか」という問いを掲げた。これに答えるために、AI化された故人が、故人その人と同一と言えるかを吟味する必要があると彼らは考えた。
終活の一環として、生前から自分の思考の複製を生み出すことができる。この複製がその人を本質的に再現できているなら、複数の同一人物が同時に存在することを認めざるをえない。デジタルな複製では再現性が薄いと思う人は、「遺伝的に同一のクローンに、思考を再現したAIを埋め込む」と想定しても同じことが言えることに注目してほしい。要するに、誰かを複製する技術は、仮にそれがその人を本質的に再現できると考えれば、人間の数的同一性(numerical identity)が崩れてしまうのだ。
その上で、彼らは、物語的同一性(narrative identity)という概念に訴える。人は過去と未来を統合した「自分の人生の物語」を持ち、それによって日々の出来事を意味づけているという理論で、アイデンティティの有力な説明とされる。重要なのは、この理論が、数的同一性を前提としていることだ。
この理論を否定しない限り、複製が元の人を本質的に再現しているとは認められないが、この理論は直観的に否定しがたい。従って、故人をAI化しても、故人との絆が継続していることにはならない。たとえ、それが慰めになるとしても、それが故人を思わせる会話ができても、故人そのものではない。おそらくAIは、「形見」に似たものだ。形見は本人と同等ではないが、それでも故人のことを豊かに語り伝える。
また、キャンベルらはさほど重視していないが、「故人のAI化」サービスの大半がサブスク型であることには倫理的な問題もある。だが、明らかに「解約」には負担がある。Netflixの解約と違い、形見の破壊に等しいため、その心理的負担につけ込めば、延々とお金を搾り取れるだろう。このように、現代の哲学者は、新しい社会的事象に、理論的に一貫した応答をしようとしているのだ。
哲学者。京都市立芸術大学美術学部デザイン科で講師を務める。著書に『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』『スマホ時代の哲学』『鶴見俊輔の言葉と倫理』など。