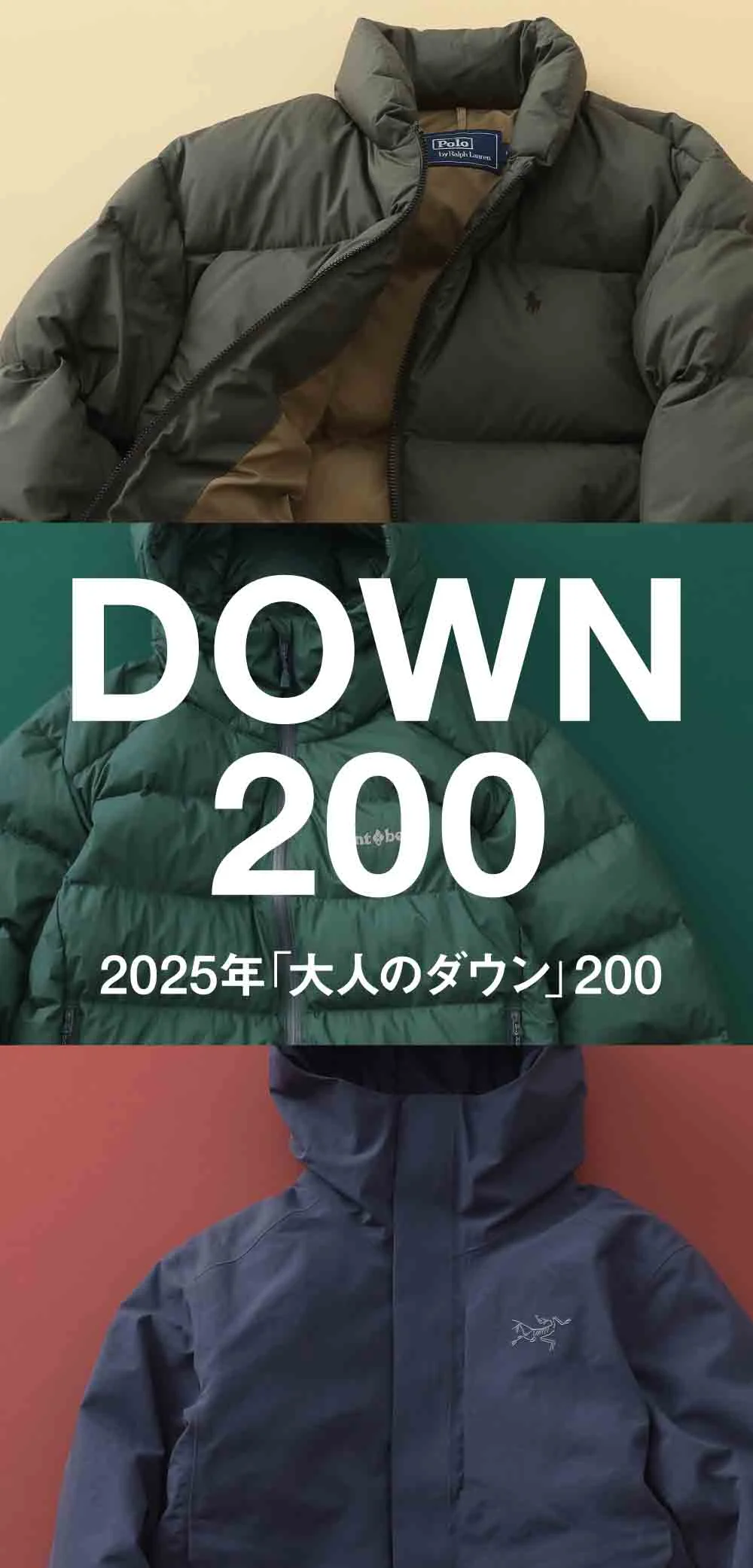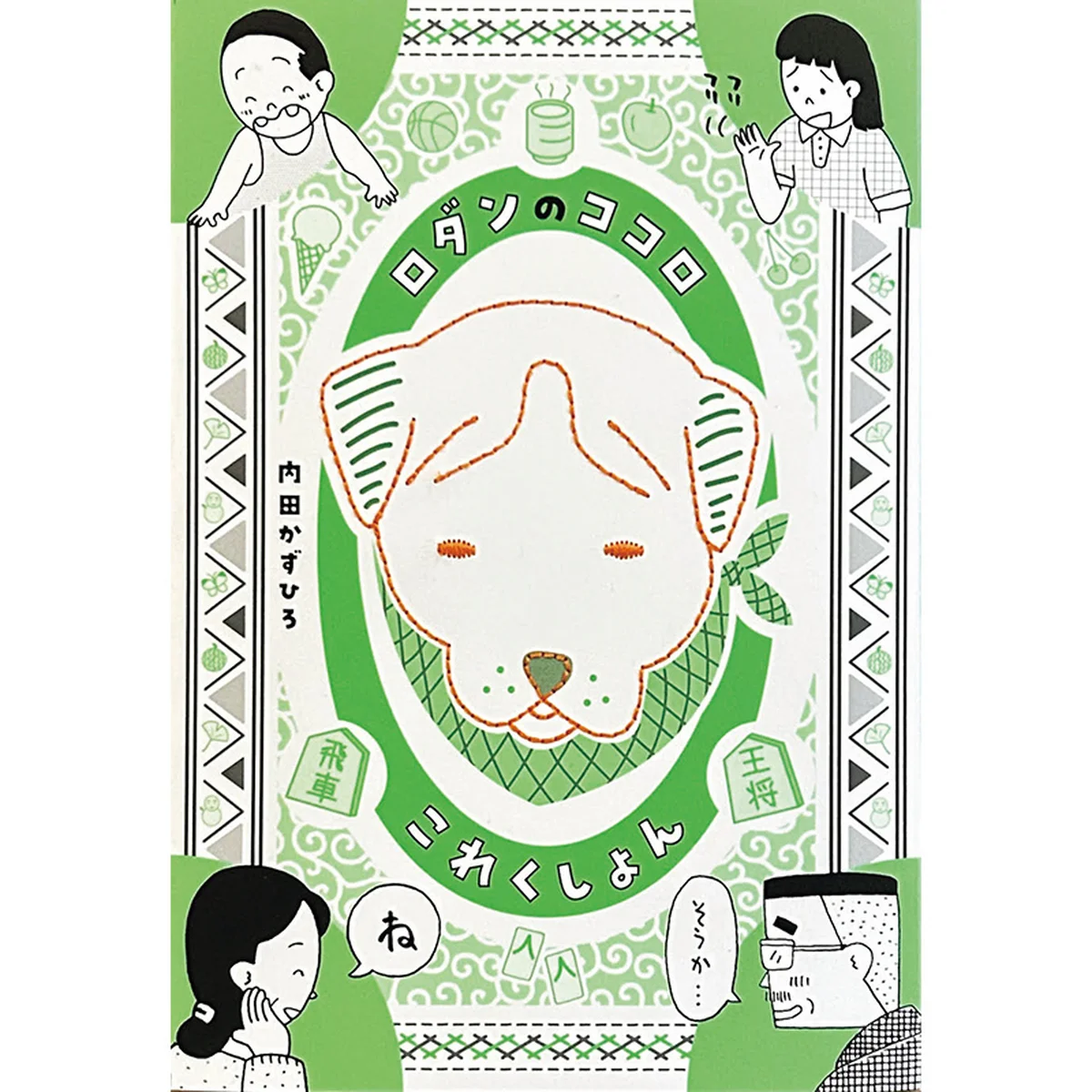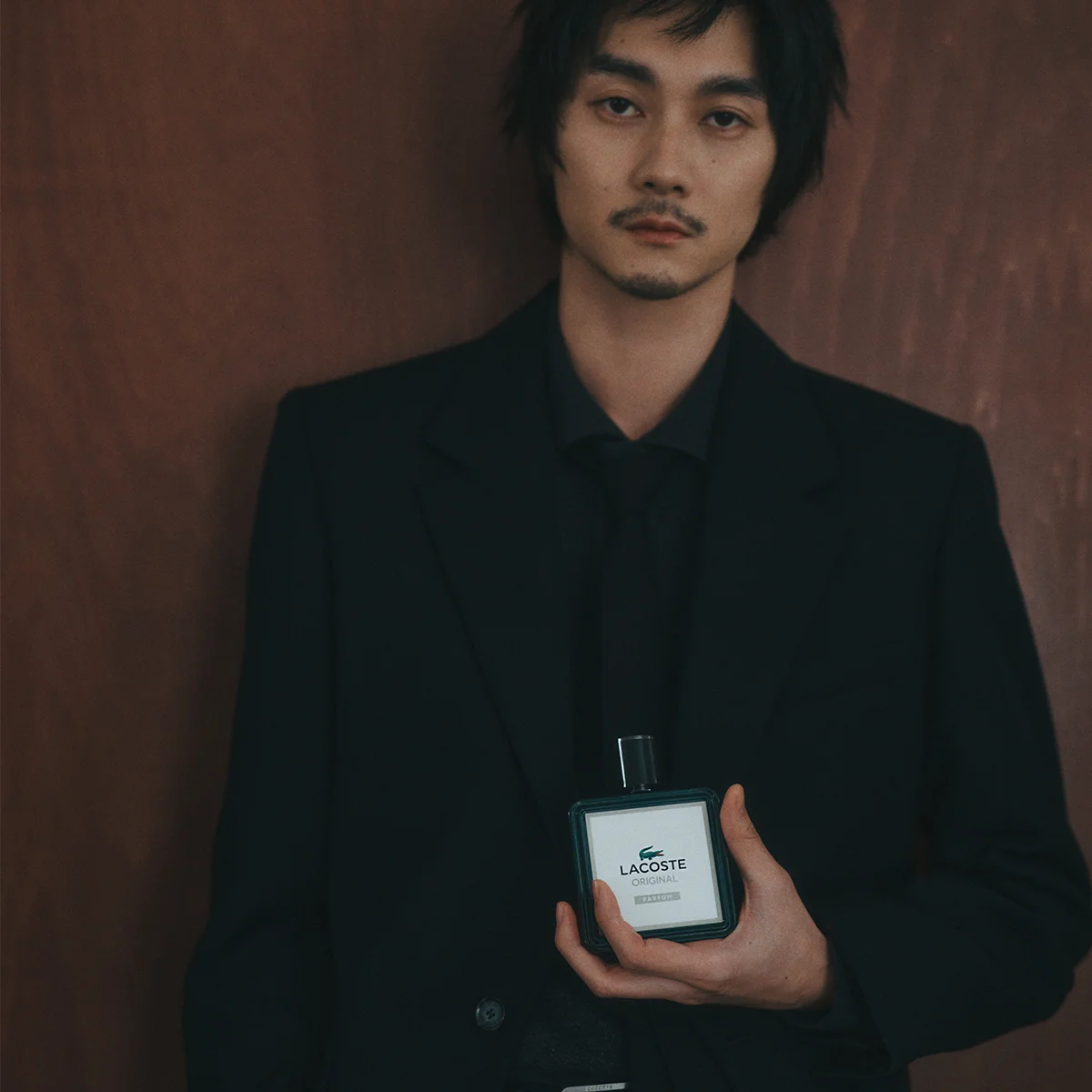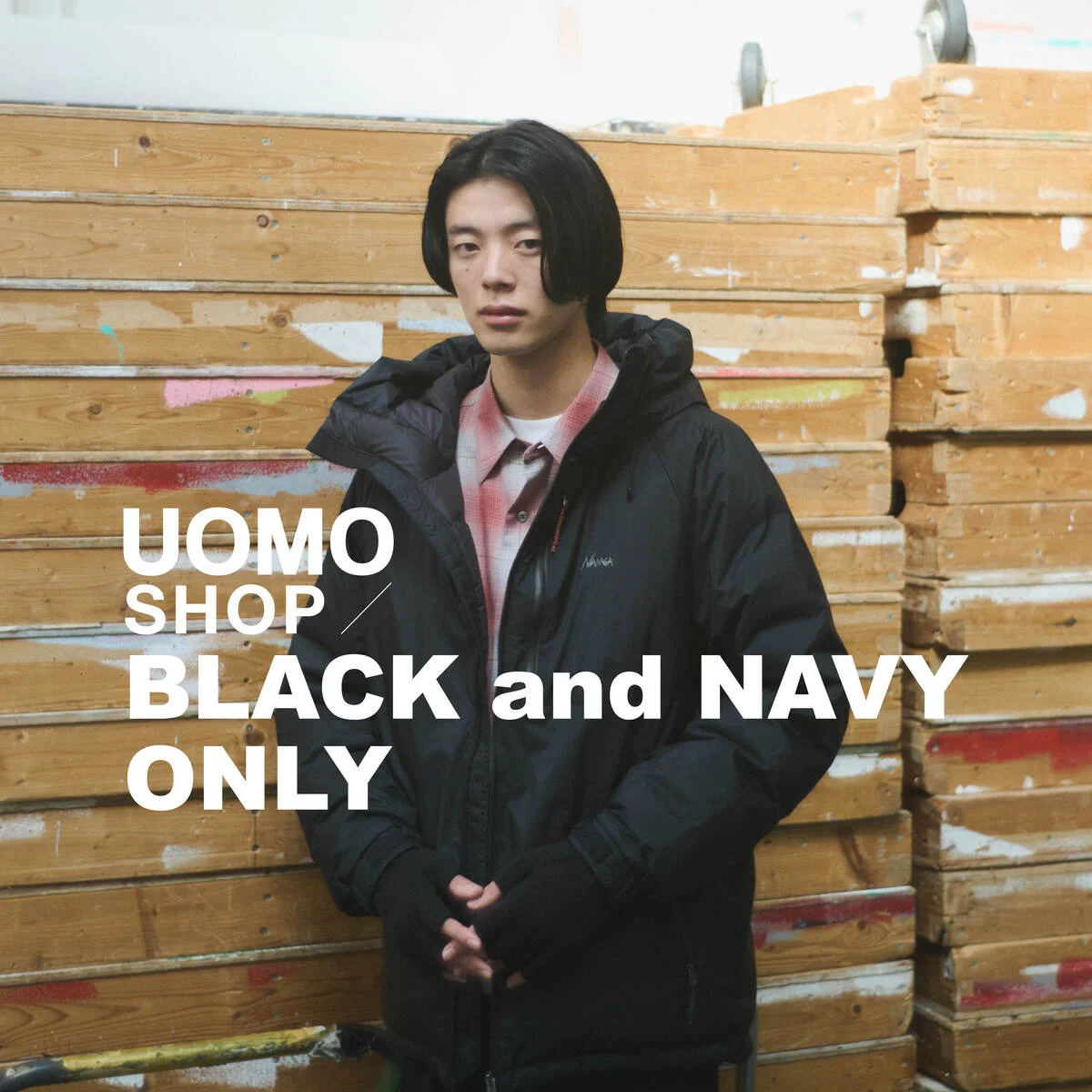第19回|Netflixは本当に「自分の好み」に従って表示されているのか?

トロントメトロポリタン大学で修士号を取得。現在は、競合企業の情報をAIで収集するサービスなどを提供する企業、Klueに所属する研究者。今回取り上げたのは「Algorithms and taste-making」という論文。嗜好集団を推定する手法を彼は「リバースエンジニアリング」に喩えている。最後に出てくる「ブルデュー」は、仏社会学者のピエール・ブルデューのこと。
TikTokやYouTubeでは視聴履歴を踏まえてパーソナライズされるので、みなが「同じ画面」を見るわけではない。2025年1月時点で有料会員数が全世界で3億人を超えたNetflixもそうだ。
Netflixのレコメンデーションシステム(以下NRS)は、ユーザー体験を個別最適化するため、プラットフォームから得た行動データを、映像作品の大規模データと組み合わせ、ユーザーを2000以上の「嗜好集団(taste communities)」に分類する。この仕組みは独自のアルゴリズムに従ってほぼ完全自動実行されている。
世の人は、アルゴリズムを「ブラックボックス」として捉えがちだ。しかし、アルゴリズムは映像文化に対して純粋に外側に立ち、ブラックボックスとして影響を与えるわけではない。NRSは、社会的・文化的・技術的慣習と組み合わさりながら、新たな文化を形成する「構築的絡まり」の下に把握すべきなのだ。
研究者のニーコ・パコヴィックは、異なるペルソナを立て、その好みに沿って毎日1つの映像を選択し、その映像に対してNetflixが割り当てたジャンルの種類を記録する作業を2週間行った。「嗜好集団」の詳細は公開されていないため、パコヴィックは①熱狂的なスポーツファン、②カルチャースノッブ、③逃避的なロマンチストの3つのペルソナを独自に設定した。
実験5日目までに、各々の趣味嗜好に沿った映像がホーム画面に表示されるようになった。③には、恋愛作品や恋愛リアリティーショーが、②には過去の名作や批評家から絶賛された海外映画が表示されるというように。興味深いのは、『アウターバンクス』や『ラ・ラ・ランド』のように、共通して表示された映像作品のアートワークの違いだ。①にはサーフィンやダンスなど動的な場面が、②には意味深な表情と構図が、③の画面にはキスシーンが表示された。
アルゴリズムを混乱させるとき、「アルゴリズムの論理が最も明確に表れる」と考えたパコヴィックは、一貫しない映像ジャンルの選択と評価を行うアカウントを並行して運用した。そのホーム画面には多様な作品が表示されていたのだが、興味深いことに、上記3つのペルソナと同じく、やけに『ワイルド・スピード(WS)』シリーズの作品が推奨されたのである。
この妙なWS推しは、一気視聴を誘い、ユーザー維持率を高めるための方略だと考えられる。普段はパーソナライズを装って隠されているが、好み集団を貫いて時折こうした方法がリテンションのために用いられるのだ。
視聴者はアルゴリズムで好みを変容させるし、アルゴリズムの動作も人々の嗜好で変わる。この相互性の実態の分析は、アマチュアの受動性を強調するブルデューへの批判にもなっている。
哲学者。京都市立芸術大学美術学部デザイン科で講師を務める。著書に『増補改訂版 スマホ時代の哲学』『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』『鶴見俊輔の言葉と倫理』など。