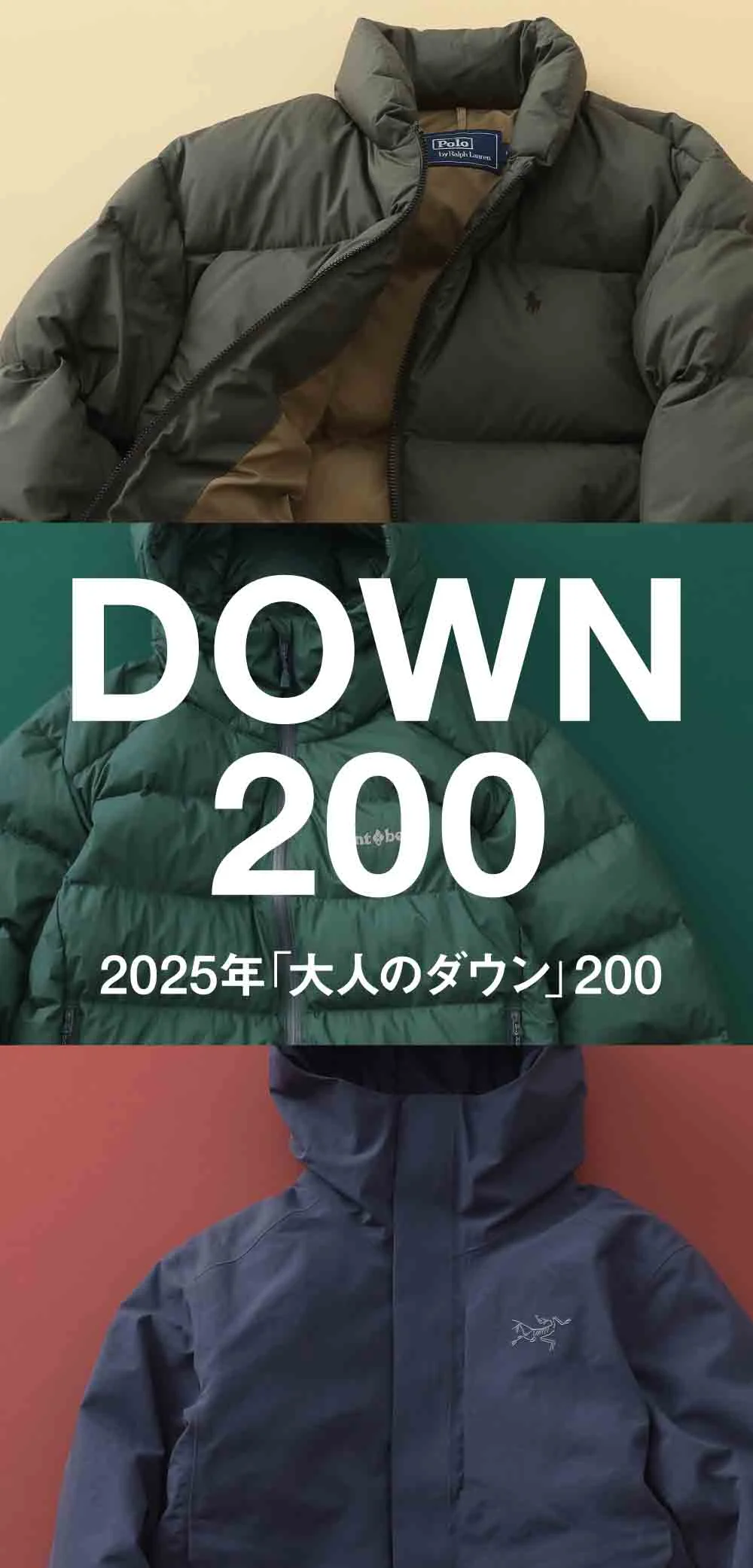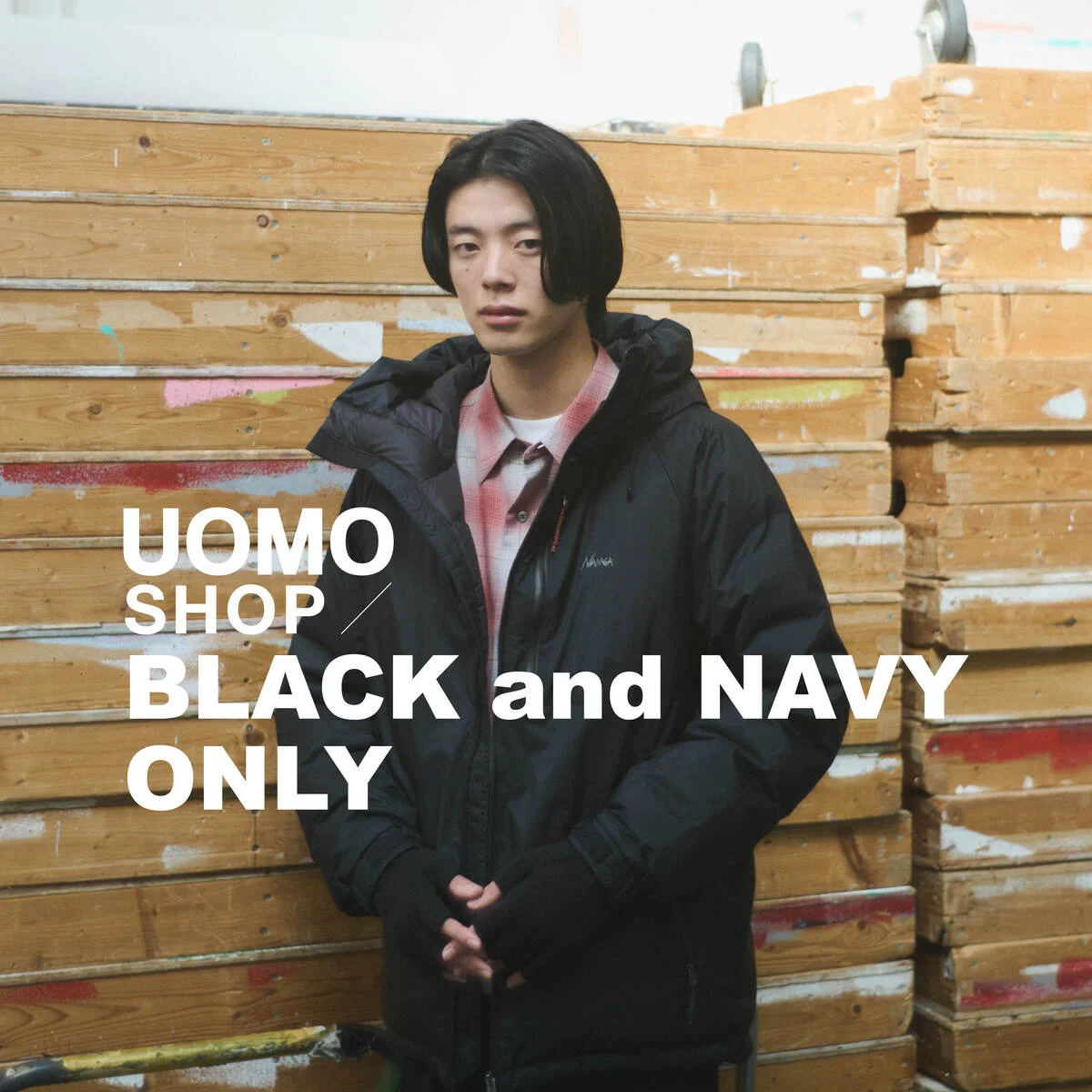近年、さまざまなLGBTQ+作品が誕生しているが、今回取り上げる『ブラザーズ・ラブ』はこれまでのものとはひと味違うようだ。ジェーン・スーと高橋芳朗は、今作をどう読み解くのか。
『ブラザーズ・ラブ』(2022年)
40代の奥手な男性同士が繰り広げる恋愛を描いただけじゃない

――今年2月、日本のNetflixで配信がスタートし、話題を呼んでいるLGBTQ+作品『ブラザーズ・ラブ』です。いかがでした?
ジェーン・スー(以下、スー):カジュアルに観られるけど、骨太な作品でもある。ヘテロ(異性愛者)の恋愛と同じところもあるし、違うところもあるし。ヘテロの恋愛もさまざまなのと同じように、ゲイの恋愛もいろんなパターンがあるわけで、これだけがゲイのラブコメというわけではないんだろうと思いながら観てました。
高橋芳朗(以下、高橋):『KISSingジェシカ』(2001年)だったり『ハピエスト・ホリデー 私たちのカミングアウト』(2020年)だったり、この連載ではこれまでにもLGBTQ+関連作品を何度か取り上げてきたんだけど、今回の『ブラザーズ・ラブ』は大手スタジオ(ユニバーサル・ピクチャーズ)が製作する史上初のゲイのロマンティックコメディなんだって。ただ、残念ながら批評家筋からの評価は高いものの興行的には大失敗だったみたい。劇中でたびたび『恋人たちの予感』(1989年)をオマージュしているように、王道のロマンティックコメディとしても楽しめる傑作だと思うんだけどな。
スー:そうなんだ……。大失敗とはにわかには信じがたい。評価と売り上げは比例しないものなのね。
高橋:2022年の全米公開直後、主役のボビー・リーバーを演じるビリー・アイクナーが「LGBTQ+コミュニティでしか話題になっていない」みたいなことをSNSでぼやいていたのが記事になっていたよ。
スー:なるほど。当事者にしか響かない物語だとも思わなかったけどなあ。とはいえ、当事者ではない私たちがこの作品について語るのは、正直とても難しいと感じてしまうところもある。
高橋:細かいジョークや「ゲイあるある」みたいなものも完璧には理解できないから。たとえば劇中でボビーが恋人のアーロン・シェパードと旅行で訪れるマサチューセッツ州の人気の避暑地プロビンスタウンは全米屈指のゲイタウンであるとか、そういう背景も知っているに越したことはないもんね。アーロンの弁護士事務所で余命わずかの身寄りがない老紳士が遺産相続の相手に歌手のシェールを挙げるシーンなんかは比較的わかりやすいギャグだと思うんだけど。この一言で老紳士がLGBTQ+コミュニティの一因であることが示唆されるというね。
スー:特に日本のヘテロだと難しいよね。そもそも文化的なバックグラウンドがわからないし。ボビーがパーソナリティを務めるポッドキャスト番組のタイトルが「The 11th Brick At Stonewall」なんだけど、まず「ストーンウォールの反乱」自体が日本ではなじみが薄い。加えて、なぜボビーが石を投げるのは11番目なのか?という点。LGBTQ +の当事者たちが政府の迫害に抵抗したストーンウォールの反乱で「おそらく最初の石を投げたのは男っぽいレズビアンや有色人種のトランス女性だと思われるけれど、シス(生まれた時の体の性と自分が認識している性が男性である人)で白人の男性だって11番目に石を投げたかもしれない」というようなことをボビーが言ってたけど、あれは自分たちの存在を皮肉を込めて表現してるよね。白人のシス男性という時点で、社会的に特権階級だとみなされるから。マイノリティのなかでも暮らしやすいほうだと認識されているんだと思われる。あのタイトルは、「白人のシス男性のゲイは運動の中心人物にはなりえない」という意味なんだろうね。出だしの5分だけでも、「40代の恋愛に奥手な白人ゲイ男性ふたりの恋物語」だけではない背景がたんまりあるんだとわかる。
高橋:冒頭、ボビーがLGBTQ+のセレモニーで「最優秀白人シスゲイマン賞」を受賞するシーンも自虐的というか風刺が効いているというか。そもそも彼がなぜあんなにも複雑に拗らせているのか、そして一見完璧に思えるアーロンがなぜまったく自信を持つことができないのか。そこを丁寧に紐解いていく必要はあると思う。

スー:主演のふたりは実際にゲイだと公言しているし、ほかの出演者たちも当事者。後半では、ヘテロの役者たちが「苦悩するゲイの役」を演じてきたことへの皮肉も言ってる。当事者性という点ではかなりの達成度があることも、今作の特筆すべき点なのかもね。
高橋:序盤にボビーが業界人然とした映画プロデューサーからゲイのロマンティックコメディ映画の製作を持ちかけられるシーンがあったけど、あれはメタ的でおもしろかった。深いドラマ性やメッセージ性、悲劇性を求められることの多いゲイ映画のステレオタイプを頭から徹底的に否定していく構成にはメジャースタジオ初のゲイロマコメとしての矜持を感じたな。
スー:ステレオタイプの否定は大きなテーマだと思う。白人のシス男性でゲイのふたりが主人公だけど、ヘテロのラブコメをなぞったものではなく、マイノリティコミュニティでの立ち位置(たとえば、11番目に石を投げる)や、ゲイの歴史がないものとされてきたことに対する怒りの表明や、ゲイカルチャーの表現、ゲイカルチャー内のマッチョ文化への反発、ゲイにとって「トーンダウンしろ」はずっと言われてきた抑圧の言葉、LGBTQ+コミュニティも一枚岩ではないこと、などなど。注意して観ていくとほんと盛りだくさんなんだよね! ボビーはなにかにつけて「アーロンはマッチョが好きで自分なんかタイプじゃない!」と言い続けるけれど、あれはゲイコミュニティではステレオタイプな男らしさが好まれる傾向にあることを表現しているわけで。
高橋:ボビーがジムでマッチョな声色を作って黒人男性をナンパするシーンもそうだし、そもそも原題の『Bros』にもそういう含意があるんだろうね。そうしたなかで印象的だったのは、ゲイ文化の商業化(クィアベイティング)にきっちり釘をさしていたこと。あと、劇中でボビーは国立LGBTQ+歴史博物館の初代館長としてその立ち上げに奔走しているんだけど、さまざまな立場の性的マイノリティで構成された学芸員とのミーティングがことごとく紛糾するくだりも興味深いものがあった。
スー:そうそう、一枚岩ではないことをうまく表してた。展示物のテーマを議論するシーンで、「博物館がクジラの骨格標本を天井から吊るすように、巨大なレズビアンの像を天井から吊るそう!」とかあったじゃない? あれは明らかに笑いを誘う場面だったけれど、ボビーは「エイズやストーンウォールや、そういったトラウマだけじゃなくて“JOY”を通してゲイカルチャーを伝えることも必要だ」と言っていて、それも大切なテーマだと思った。あと、ゲイであることをすでに家族に受け入れられているアーロンでさえ、家族の前ではゲイっぽさを控えるよう努めてしまうし、家族に紹介したときにはボビーにもそれを求めてしまう葛藤とか。ラブコメ的なご都合主義はもちろんあるけど、本作は多層的なんだよね。
高橋:世界各地でテスト上映を繰り返したのに加えて、LGBTQ+専門の学者がアドバイザーとして製作に参加しているみたいだからね。相当慎重に作られているのはまちがいない。
スー:恋愛に奥手な中年男性ゲイのラブコメとして、非当事者にも理解できるストーリーではありながら、LGBTQ+コミュニティの内情や現在の問題点などについても文化的背景をちりばめながら物語が進んでいくから、理解度が試される作品ではある。
高橋:物語の理解を深める意味でも主役のふたり、ボビーとアーロンのパーソナリティーとバックグラウンドについて改めて整理しておこうか。まずゲイのタレントにして100万人のリスナーを抱えるポッドキャスターでもあるボビーは偏屈な拗らせキャラで皮肉屋。40歳にしてまともに恋愛をしたことがなくて、ゲイのコミュニティに対するスタンスもひねくれてる。曰く「ゲイは信用できない」。一方、ゴーゴーボーイ風のセクシーな風貌のアーロンは遺産相続を専門に扱う弁護士。でも、本当はショコラティエになりたいという幼いころからの夢がある。周囲から「退屈な体育会系筋肉バカ」と思われていること、そしてゲイである自分自身に誇りが持てないことにコンプレックスがあって、LGBTQ+の権利を声高に訴える自信に満ちあふれたボビーに対して憧れを抱いている。アーロンの内包する劣等感みたいなものは彼がLGBTQ+歴史博物館でひとり佇みながら内省する場面にわかりやすく描かれているね。
マライア・キャリーの楽曲はゲイにとっての賛歌

スー:ボビーもアーロンもコミットメントフォビア(深い関係、特に恋愛や結婚、家庭を築くことに対して、強い不安や恐怖を感じる心理的な状態)なのよ。でも、セックスは簡単にする。ゲイ男性向けのアプリがあるから、彼らにとってセックスは簡単に手に入るものなんだよね。性欲のみで、後腐れもない。セックス描写はかなり多かったね。レズビアンの恋愛を描いた『ハピエスト・ホリデー 私たちのカミングアウト』ではセックスの話がほとんど出てこなかったのとは対照的に。
高橋:ナット・キング・コールの「When I Fall in Love」をバックにボビーとアーロンがベッドでじゃれ合うシーンが素敵だったな。ふたりのキスのタイミングがいちいちエモーショナルなのもすごくよかった。そしてエモーショナルといえば、大団円のボビーのスピーチと彼が書き下ろしたオリジナルソング「Love Is Not Love」(愛は単純じゃない)。最後のスピーチで泣かせにかかるのはロマンティックコメディのお約束だけど、これは歴史的に見てもなかなかの破壊力だと思う。詳細は避けるけど、アーロンの音楽趣味に応じてあえてカントリー調で歌った「Love Is Not Love」は冒頭で映画プロデューサーが主張していた「Love is love is love」へのアンサーにもなってるんだよね。
スー:確かに!「ゲイならマライア・キャリーが好きでしょ!」って態度のボビーと、ガース・ブルックス(保守的なジャンルであるカントリーの歌手)が好きなアーロンという対比を見せる場面が冒頭にあったけれど、あの回収になってる。
高橋:製作陣についても触れておきたいんだけど、プロデューサーのひとりとしてジャド・アパトーが名を連ねていることは強調しておきたい。『40歳の童貞男』(2005年)だったり『ブライズメイズ 史上最悪のウェディングブラン』(2011年)だったり『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』(2017年)だったり、やっぱり彼はこれまで描かれることのなかった立場の人たちにスポットを当てた新しいラブコメディを作ることにめちゃくちゃ意識的なんだなって。その試みのすべてがうまくいっているとは言えないかもしれないけど、彼の試行錯誤は支持したいし今後も注目していきたいね。監督を務めているのもジャド・アパトー組で今年に入ってからプライムビデオで配信されたウィル・フェレルとリース・ウィザースプーン主演のラブコメディ『真心を込めて招待します』でメガホンを握っていたニコラス・ストーラー。彼はジェイソン・シーゲル主演『寝取られ男のラブ♂バカンス』(2008年)やセス・ローゲン製作/主演の『ネイバーズ』(2014年)を撮っているけど、ゲイのラブコメディは彼がずっと温めていた企画らしい。そのあたり、アパトーと共鳴するところがあったんだろうな。
スー:なるほど、そういう経緯があったのね!
高橋:それからこれは先ほども触れた物語の理解度に通じる話だけど、劇中ではいろいろな映画やドラマが引き合いに出されていて。『ユー・ガット・メール』(1998年)、『ハングオーバー』(2009年)、『グレイテスト・ショーマン』(2017年)『ボヘミアン・ラプソディ』(2018年)など、挙げていくとキリがないんだけど、なかでは『恋人たちの予感』のオマージュを随所に挟み込んでいたのがグッときた。これはこの作品をロマンティックコメディの系譜のなかに置いて評価してほしい、という作り手の意志の表れでもあるんじゃないかな。ドラマの引用ではゲイのジェネレーションギャップを「We had AIDS, and they had Glee」(我々にはエイズが、彼らには『glee/グリー』があった)と表現していたのがインパクト大だった。キャストに関しても『トーチソング・トリロジー』(1988年)でおなじみのハーヴェイ・ファイアスタインや『ウィキッド ふたりの魔女』(2024年)でグリンダの取り巻きを演じていたボーウェン・ヤンといったゲイであることを公言している俳優が脇を固めていたり、ゲイ男性の弁護士ウィルとインテリアデザイナーの女性グレイスの友情を軸にしたドラマ『ふたりは友達? ウィル&グレイス』(1998年~)のグレイス役だったデブラ・ミッシングが本人役で出演していたり。

スー:デブラもそうだけど、今作はかなりカメオ出演が多いよね。ベン・スティラーやエイミー・シューマー。他にも、映画やドラマで見たことある人が多々登場するから、それを見つけるのも楽しいかも。そういえば、多数派から拒絶反応を示されない「都合のよいゲイ」の象徴として、Netflixの人気番組『クィア・アイ』(2018年〜)の登場人物を模したと思われる人たちも出てきてたね。ファブ5のことを、多数派にとって都合のよい状態にウォッシュされたマイノリティという捉え方をしているんだろうな。ゲイが商業的にマジカルニグロ(白人が制作する映画に出てくる典型的な都合のよいキャラクター)化しているとも捉えられるっていう皮肉だね。ラブコメは頼りになるゲイの男友達っていう役でそれをやりまくってきた前科があるからな……。最後にヨシくんに音楽についても聞いておきたい! マライアの愛され具合とか、カントリーミュージックがなぜゲイフレンドリーではないとされているのかとか。どう?
高橋:マライアは「ヒーローはあなた自身の中にいる」と説いて聴き手を鼓舞する「Hero」(1993年)や彼女の人種的バックグラウンドに基づく疎外感を歌った「Outside」(1997年)などがLGBTQ+コミュニティでアンセム化している背景があるし、2016年にはGLAAD(中傷と闘うゲイ&レズビアン同盟)主催のアワードでアライ賞を受賞していたりする。あとカントリーミュージックにおけるLGBTQ+の歴史と現状についてはTBSラジオ『アフター6ジャンクション』2022年4月26日の放送で解説したことがあるから詳しくはそのポッドキャストを聴いてもらえると。保守層に支えられているカントリーミュージック業界では長らくLGBTQ+の不当な扱いが問題視されてきた経緯があるわけだけど、同性愛に言及した「Follow Your Arrow」(2013年)のヒットでLGBTQ+アイコンになったケイシー・マスグレイヴスのような新世代の登場によって状況は大きく変わりつつあって。2022年の第64回グラミー賞では兄弟デュオのブラザーズ・オズボーンが歌った「Younger Me」がLGBTQ+を題材にした楽曲として史上初めてカントリー部門の受賞を果たしていたりする。ちなみに、アーロンが好きなガース・ブルックスは1992年に発表したプロテストソング「We Shall Be Free」で飢餓、貧困、人種差別などと共に同性愛嫌悪についても言及していて。その結果彼はLGBTQ+コミュニティへの貢献を評価されてGLAADのアワードを受賞することになるんだけど、一方でガースはこの曲で初めてカントリーシングルチャートのトップテン入りを逃しているんだよね。
スー:プロテストソングを歌っていたことも、それでチャートインを逃したことも知らなかったわ。いやあ、ちょっとそれは悔しいね。でも意味のある事だったと思う。
高橋:この流れで劇中の音楽について簡単に触れておくと、クライマックスの伏線にもなるボビーの愛唱歌は映画『ダーティー・ダンシング』で主演のパトリック・スウェイジが歌った大ヒット曲「She's Like the Wind」。スウェイジはドラアグクイーンのロードムービー『3人のエンジェル』(1995年)で主演を務めた経歴があるね。そしてプロビンスタウンのビーチでボビーとアーロンが心を通い合わせる重要シーンで流れるのが、イギリス人シンガーソングライターのジョーン・アーマトレーディングが1976年に放ったヒットシングル「Love and Affection」。彼女は自分のセクシャリティを明らかにしてはいないんだけど、同性婚をしていることなどからLGBTQ+コミュニティでは昔から一定の人気があって。この曲はタイトル通り恋愛感情未満の愛について歌ったラブソングで、きっと「私はひとりでも強く生きていける。強がってるだけかもしれない。でも時々、誰かの腕の中でただ泣きたいだけの時もある」という歌詞が共感を集めているんだろうね。
スー:その気持ちには多くの人が共感できるんじゃないかな。
高橋:作品の性格上、普段より補足や注釈が多くなって敷居の高い印象を与えてしまったかもしれないけど、ラブコメウォッチャー的に無視できない作品ではあるのは確か。商業面での失敗はともかくとして、この映画の意義はきっとのちのちまで語り継がれていくことになると思うよ。
『ブラザーズ・ラブ』
監督:ニコラス・ストーラー
脚本:ジャド・アパトー、ニコラス・ストーラー、ジョシュ・チャーチ
出演:ビリー・アイクナー、ルーク・マクファーレン、アマンダ・ビアース、ガイ・ブラナム
製作:2022年(アメリカ)
Photos:AFLO
PROFILE
東京生まれ東京育ちの日本人。TBSラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」、ポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香の『OVER THE SUN』」のパーソナリティとして活躍中。『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』(幻冬舎文庫)で第31回講談社エッセイ賞を受賞。著書に『生きるとか死ぬとか父親とか』(新潮文庫)、『私がオバさんになったよ』(幻冬舎文庫)、『これでもいいのだ』(中央公論新社)、高橋芳朗との共著に『新しい出会いなんて期待できないんだから、誰かの恋観てリハビリするしかない 愛と教養のラブコメ映画講座』(ポプラ社)、『闘いの庭 咲く女 彼女がそこにいる理由』(文藝春秋)など多数。
東京都出身。著書は著書は『マーベル・シネマティック・ユニバース音楽考~映画から聴こえるポップミュージックの意味』(イースト・プレス)、『新しい出会いなんて期待できないんだから、誰かの恋観てリハビリするしかない~愛と教養のラブコメ映画講座』(ポプラ社)、『ディス・イズ・アメリカ~「トランプ時代」のポップミュージック』(スモール出版)、『ライムスター宇多丸の「ラップ史」入門』(NHK出版)、『生活が踊る歌~TBSラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」音楽コラム傑作選』(駒草出版)など。出演/選曲はTBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』『アフター6ジャンクション』『金曜ボイスログ』などがある。