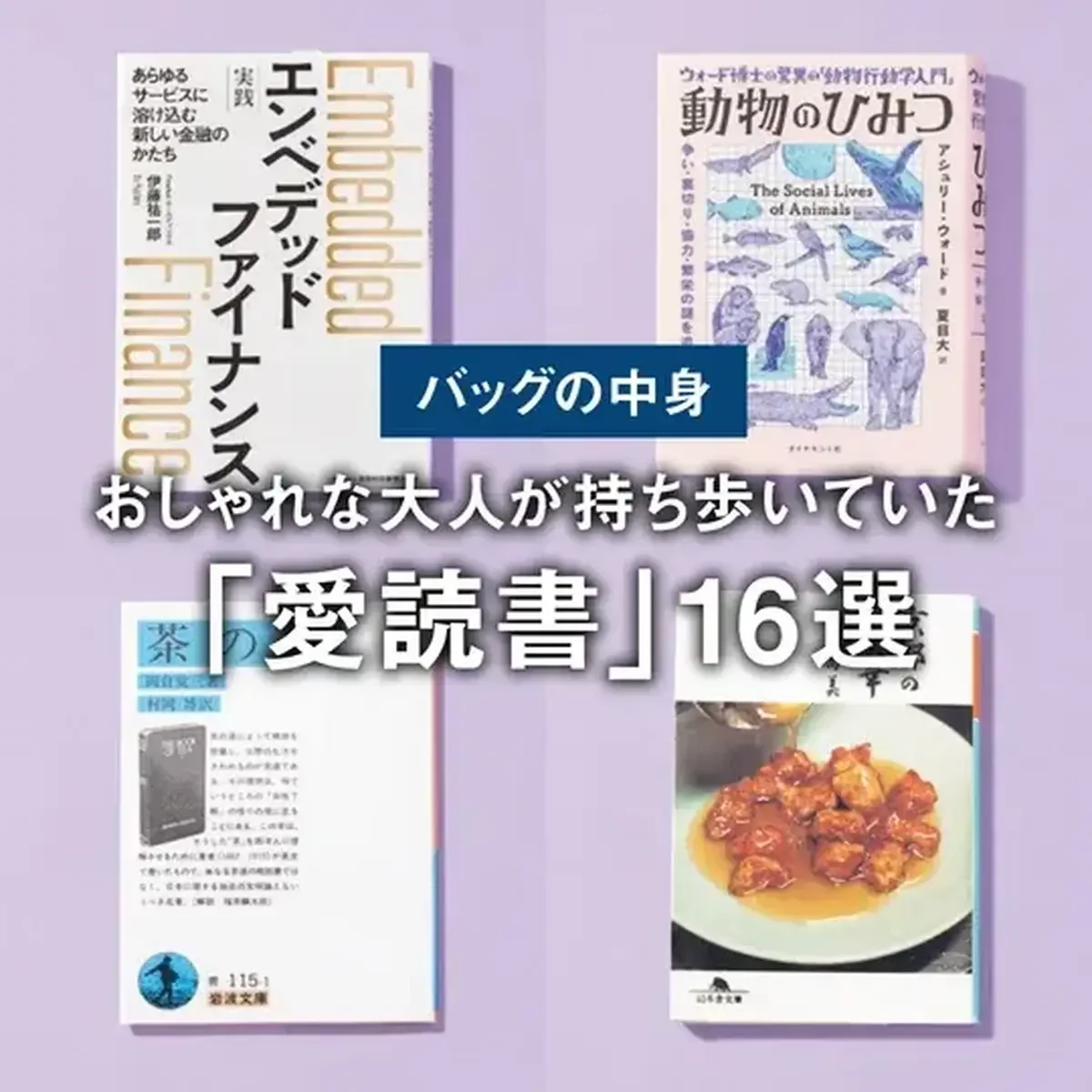『機械・春は馬車に乗って』

仕事に飲みこまれるうちに
自分が「役割」だけになる
横光利一の「機械」(一九三〇)を読むと、「仕事が人間をどう変えるか」を考えてしまいます。
〈私〉は、ネームプレート製造所という小さな職場で、人体に悪影響のある薬品を扱う〈いやな仕事〉を任され、先輩の軽部からも見下されています。
でも主人(社長)に気に入られ、暗室で行われる化学研究にかかわりはじめると、仕事の意味は一変しました。危険な作業が「特別な役割」に変わり、暗室に出入りできるかどうかが職場内の立場を左右するようになったのです。技術よりも「どこにアクセスできるか」が権力になるわけです。
そこに屋敷という職人が応援で加わった日から、職場の空気は俄然緊張しました。屋敷は頭が切れ、〈私〉の能力も見抜きます。軽部は嫉妬と疑念を刺激され、屋敷と〈私〉をスパイ視して、暴力沙汰にまで発展しました。小さな製作所での単純作業が、いつしか人間同士のプライド争いや「役割」の奪い合いの舞台になり、仕事は苛立ちを増幅させる装置となっていきます。
小説のラスト一段落の急展開には息を呑みました。ある意味実験的なミステリ小説。仕事を通じて築いたはずの関係は不信と疑念に変わり、〈私〉自身も、自分がなにに突き動かされてきたのかわからなくなります。危険な作業をくり返すうちに感覚は摩耗し、歯車のように働く自分だけが残る。
僕は作中の工場の人々とはまったく違う労働環境に身を置いていますが、それでも、彼らが感じたものがわかる気がします。専門性が突然無効化される恐怖、情報格差やアクセス権限による不公平感、そして自分を見失う感覚。この屋敷というヘルプ要員って、ひょっとしたら職場に投入されたAIだったんじゃないか。
二万字あまりの短い小説とはいえ、改行が七箇所しかない。吉田健一や筒井康隆の『虚人たち』を思わせる、読点が極端に少なく、引用符もない、稠密で息継ぎの難しい文章。それがまた作品のテンションを上げています。そういえば新潮社は筒井康隆による「機械」の朗読音源をリリースしたことがあります。改めて配信してくれないかな。
『機械・春は馬車に乗って』
横光利一著
新潮社 ¥693
作者は1898年福島県生まれ。千葉・東京・山梨・三重・広島・滋賀など各地を転々として育つ。早稲田大学専門部政治経済科除籍後、「日輪」「蠅」で小説家としてブレイク、川端康成らとともに「新感覚派」と呼ばれる。1947年没。本書収録作は作風・手法がバラエティに富み、ひとりの作家が書いたとは思えないほど多様。他に『上海』『家族会議』『愛の挨拶・馬車・純粋小説論』(すべて講談社)、『旅愁』(岩波書店)など。
文筆家、俳人。パリ第4大学博士課程修了。著書に『青ひげ夫人と秘密の部屋』(光文社)、『人はなぜ物語を求めるのか』(ちくまプリマー新書)など。訳書にトマス・パヴェル『小説列伝』(水声社)。