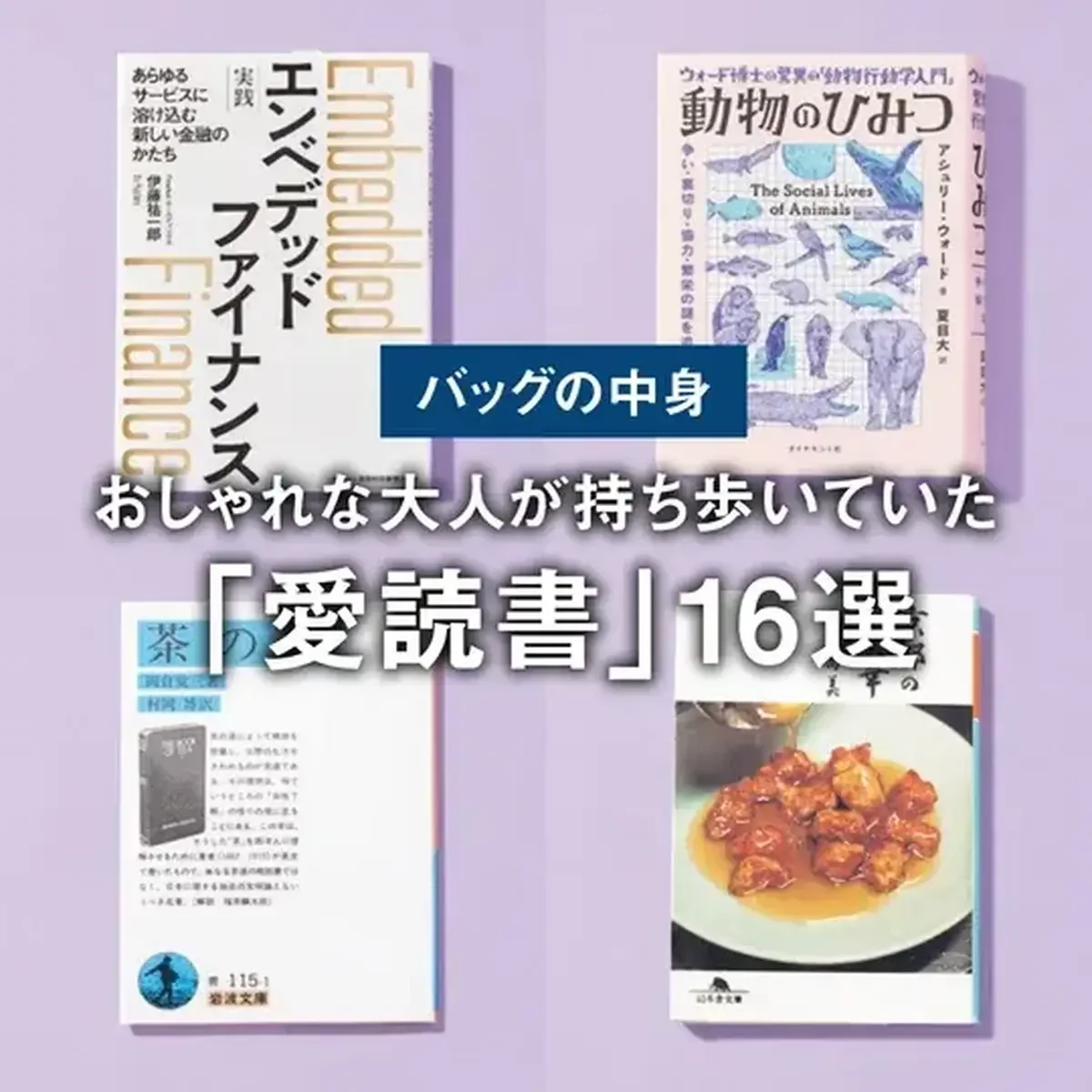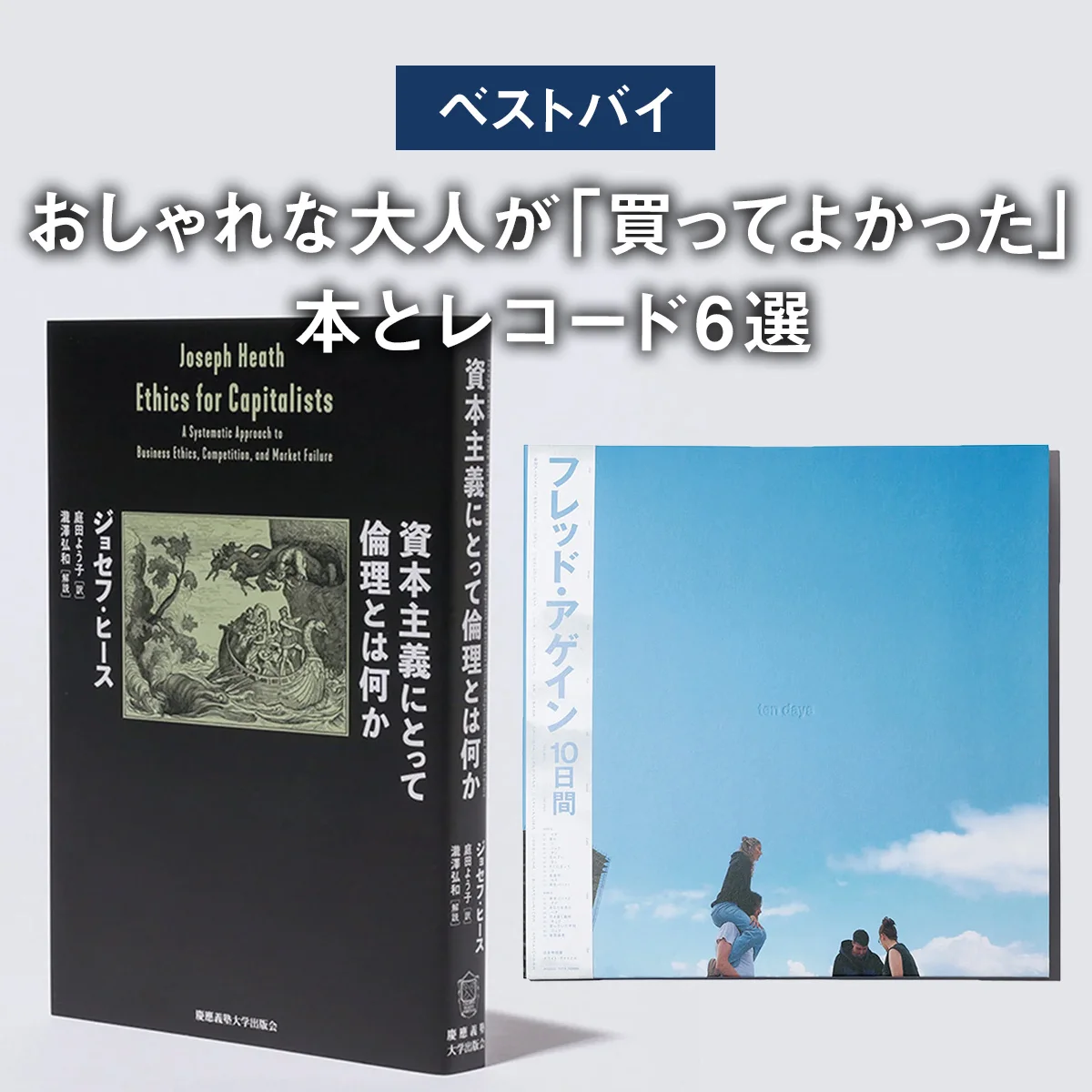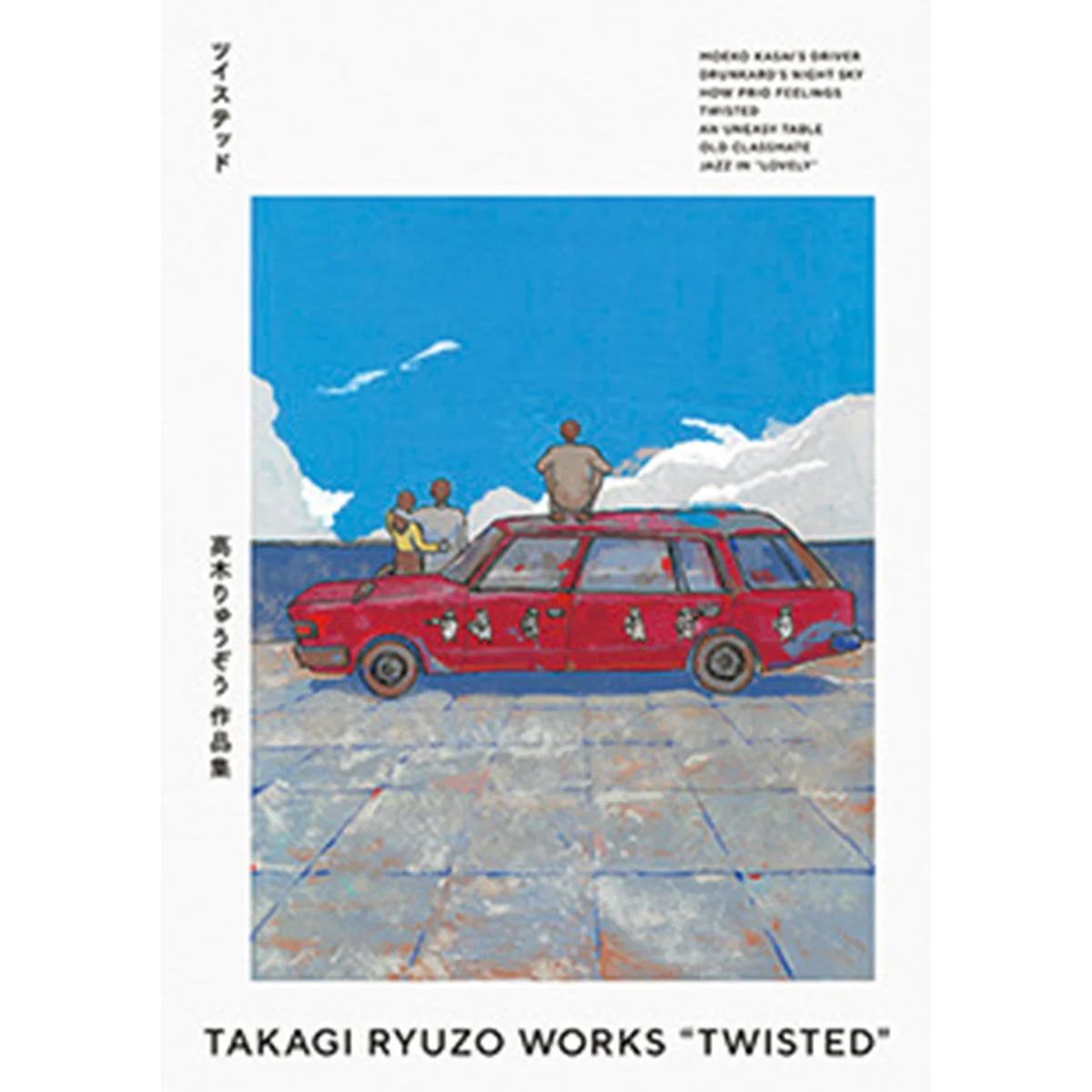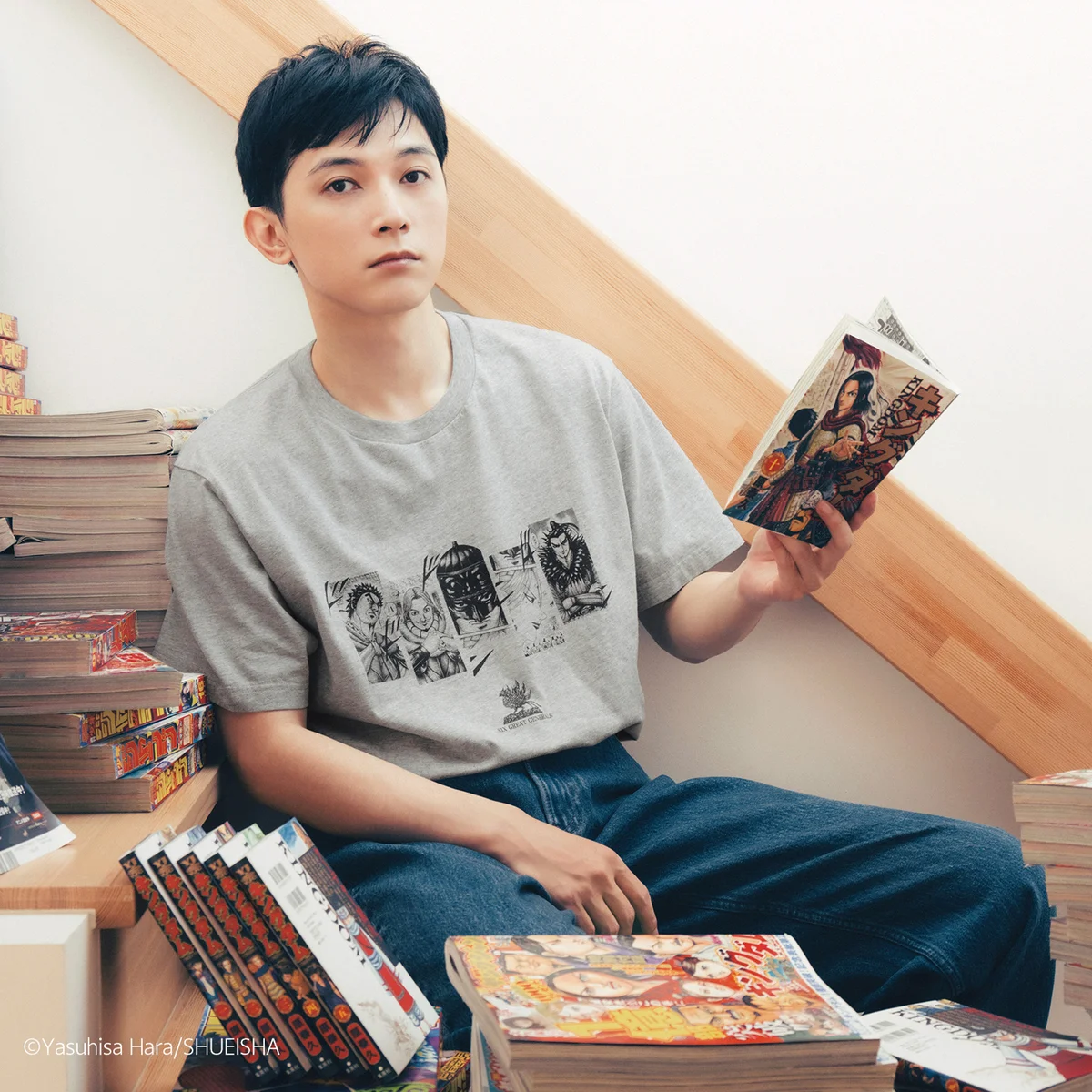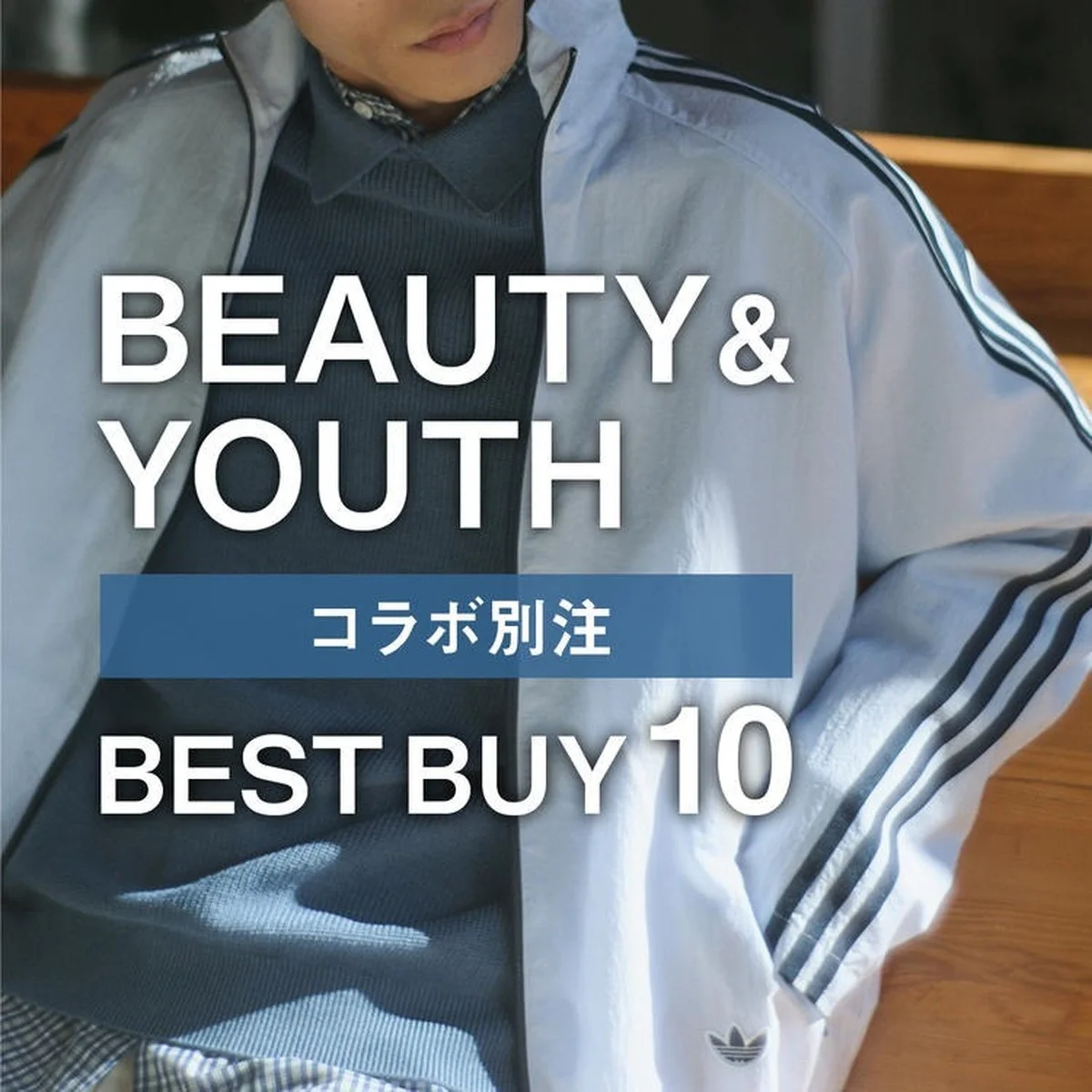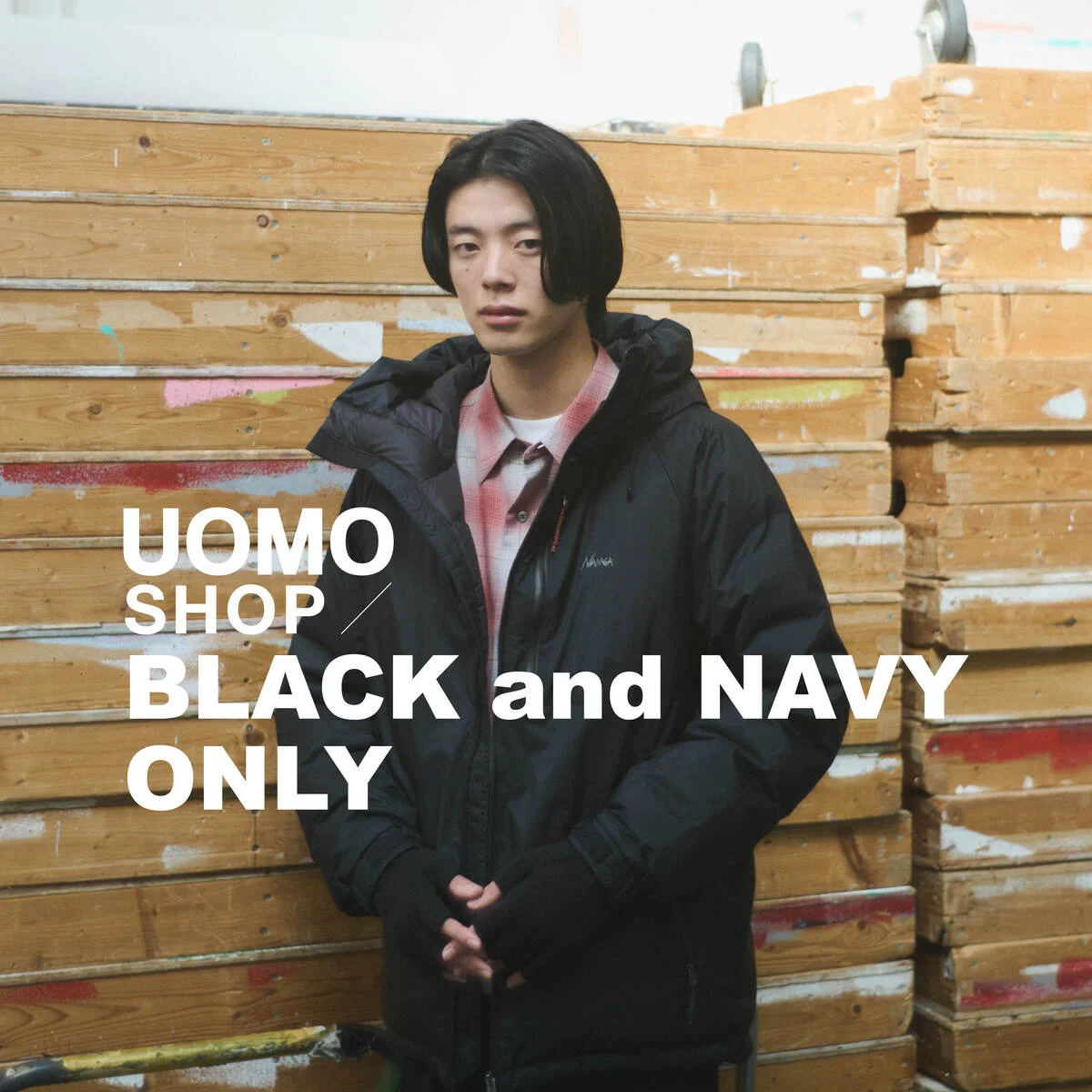『仕事と江戸時代—武士・町人・百姓はどう働いたか』

職種を「業界」ではなく
「渡世」としてとらえてみる
無駄を省いてスマートに仕事を合理化できたらいいなと思ってました。スタッフ揃って挨拶、親睦を深めると称して飲み会、非公式情報の伝言ゲーム、全部いらないんじゃないかと。でもコロナ自粛のテレワークで減ったストレスもあったいっぽう、「こんなはずじゃなかったぞ」も出てきたわけです。
なにが必須でなにが無駄か、早計に判断しちゃマズいかも、と思うようになりました。仕事の本質って意外に「なんでこんなことやってんだろ」という泥臭さにあるのかな。泥臭い要素が、なぜかその仕事を「仕事」たらしめてたりするのかもしれない。その可能性にたいして謙虚でありたいです。
こうなると自分の知らない仕事の話がおもしろい。『仕事と江戸時代』でまず目を引くのは、当方が歴史に不案内・不勉強で知らなかった数々の情報ですね。幕府勘定所には鍵番という人力タイムカードがあったとか。武士の俸給制度も制度設計と社会の実態の乖離で不都合が多かったとか。〈松屋銀座の敷地分を銀座中央通りの西側に折り返して合わせれば一つの「町」の広さ〉というのはわかりやすい説明。
茅場町・小伝馬町などの町人地、駿河台・霞が関といった〈俚俗地名〉、九段坂・紀尾井坂などの「坂」つき地名の多くが武家地、というのは初めて知りました。そういやアイドルグループの坂道シリーズには「武家の娘」感あるかも、と一瞬思ったけど、出発点の乃木坂は乃木大将で、明治までは幽霊坂でした。まったく関係なかった。
町人の自営は人別帳では〈味噌渡世〉〈呉服渡世〉〈人宿渡世〉など「◯◯渡世」と記録されている。きょうから職種を「業界」ではなく〈渡世〉としてとらえ直してみようと思った。
僕は落語が好きなんですが、そこに出てくる長屋の〈裏店〉というのが、表通りから見てどういう位置にあるのか、本書を読んでやっとクリアに。職人は特定の店に所属しない自立労働者だったし、大店の奉公人の多くが期間雇用だったというのも、今回初めてちゃんと知りました。後半の農業・漁業・鉱山・土木・輸送のリアルも、時代劇からは見えてこない世界でした。
『消費と労働の文化社会学』
戸森麻衣子
筑摩書房 ¥1,012
著者は1975年埼玉県生まれ。学習院大学文学部史学科卒業、東京大学大学院人文社会系研究科日本文化研究専攻日本史学専門分野博士課程修了。早稲田大学エクステンションセンター講師、東京農業大学非常勤講師。著書に『江戸幕府の御家人』『大江戸旗本 春夏秋冬』(ともに東京堂出版)、共著に西宮神社文化研究所編『えびすさま よもやま史話 「西宮神社御社用日記」を読む』(神戸新聞総合出版センター)など。
文筆家、俳人。パリ第4大学博士課程修了。著書に『青ひげ夫人と秘密の部屋』(光文社)、『人はなぜ物語を求めるのか』(ちくまプリマー新書)など。訳書にトマス・パヴェル『小説列伝』(水声社)。