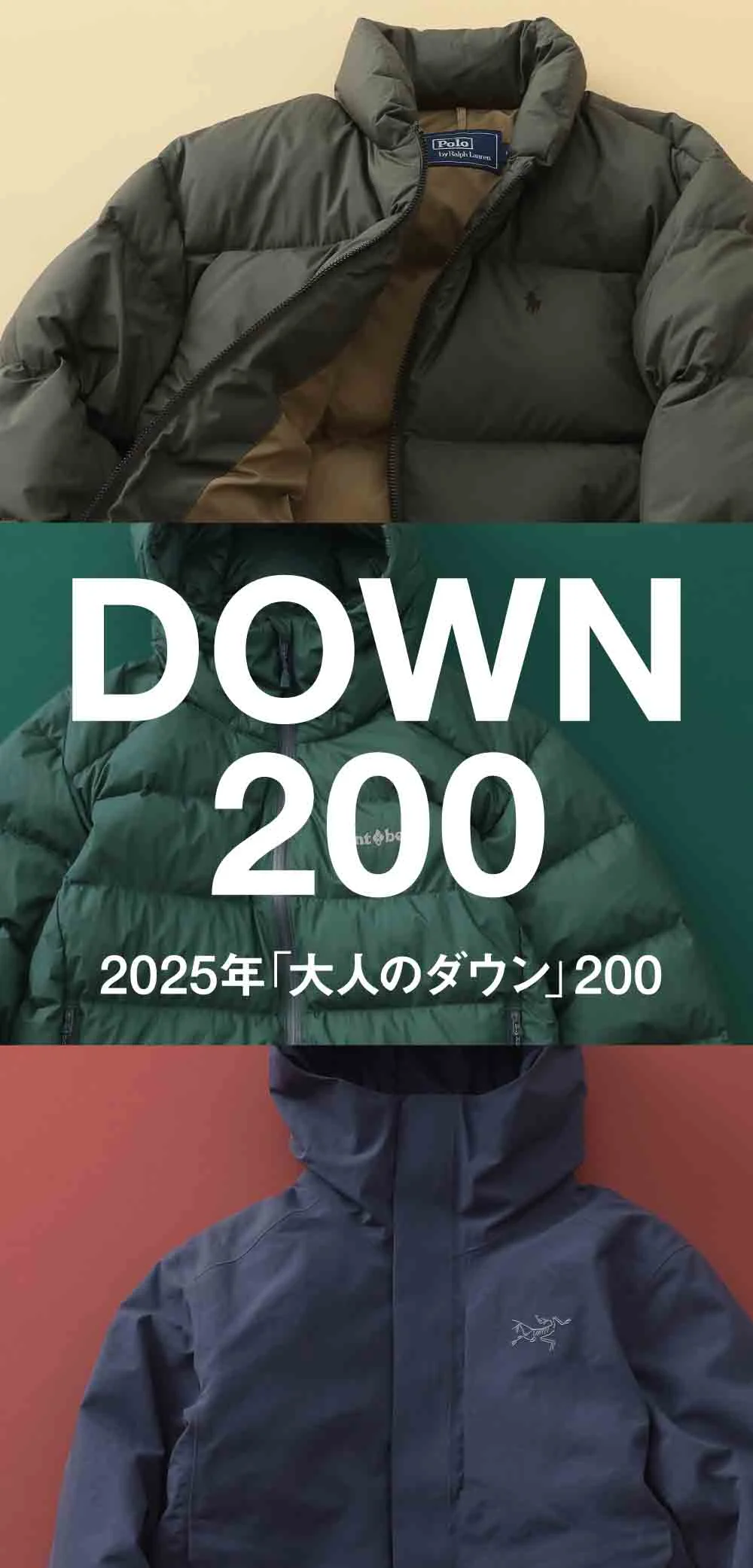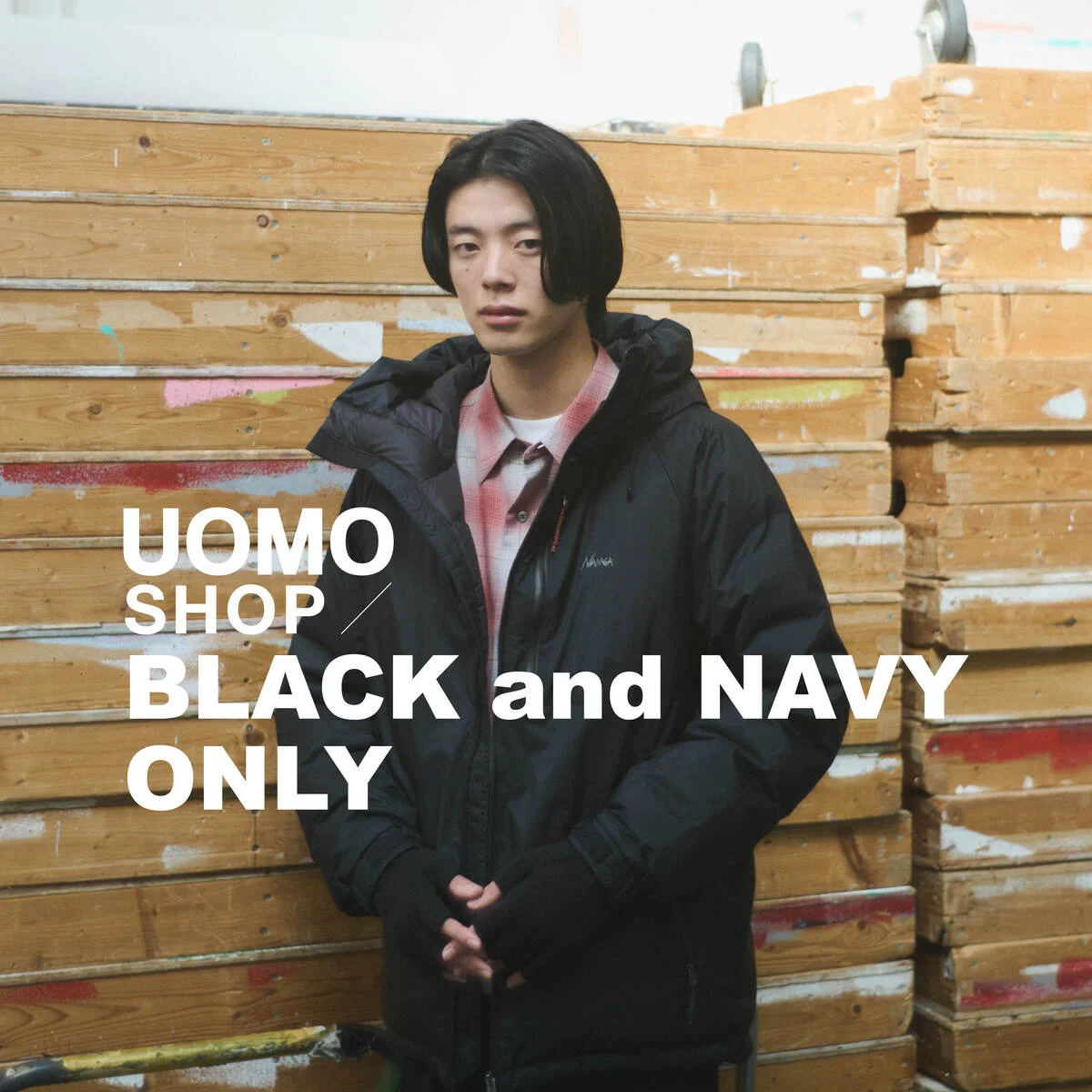読書をすることは自身の武器になり、血と肉にもなる。千野帽子さんお薦めの今月の一冊は?
『翻訳者の全技術』

もっと報われるべき翻訳者の
仕事術・思考・経験・ぼやき
山形浩生さんは経済・社会・IT・進化・サブカルチャー・現代文学・アート・古典と、多様な本を信じられない速度で訳してきた。本書で翻訳の話は三章立ての一章。二章は読書、三章は本で得られない経験の話。全部がつながってるのは、読めばすぐわかる。
興味を持った書物(未訳のもの、既訳がわかりにくいもの)を理解するために、原書の最初と最後、そして途中の気になる部分を断片的に訳すうちに、虫喰い状に訳稿が積み上がり、自分だけで持っているのももったいないのでウェブで公開、そうこうするうちに刊行の話がきたり、残りを全部訳し終わってしまったり、といったケースが多いという。翻訳活動は、山形さんの読書のサイクルの一部分を担ってきたわけだ。
二章では、自分がかつてなにに憧れ、どんな思いこみをしていたか、じっさいに本を読んでその予想がいかに打ち破られたかを、率直かつ叙情的に語る。その〈幻滅〉にこそ希望があり、そこにこそ読書の効能がある。本を読んで大人になるとはなにか、こんなわかりやすい説明はない。
ジェネラリスト的な可能性を広げてくれたのは、自身の〈腰の据わらなさや断言できなさ〉だった、と著者は言う。〈結論が出せないことに居心地の悪さを覚えている人には、それは将来の可能性につながることもあるから焦らなくてもいい、と言いたい〉。
あとがきでは、山形訳のクルーグマンが一部経済学者コミュニティで冷遇気味だとぼやいている。山形さんの著書『たかがバロウズ本。』(大村書店)も僕が読んだ米文学関連書では指折りの名著なのに、研究界では〈完全に黙殺〉、〈そもそも山形について触れるはおろか、宴会で偶然同席するのさえタブー〉らしい。これには驚いた。
経済学も米文学も素人の僕はこういう事情に疎く、わけがわからず笑うしかない。ひどすぎるでしょう(笑/怒)。帯文〈もっと山形浩生は報われていい〉(読書猿)はそういうことだったのか。同意する。
『翻訳者の全技術』
山形浩生著
星海社 ¥1,430
著者は1964年東京都生まれ。東京大学大学院工学系研究科修士課程で都市工学を専攻、マサチューセッツ工科大学不動産センター修士課程修了。野村総合研究所研究員を経てコンサルティング会社チーフエコノミスト。著書『新教養主義宣言』(河出文庫)、訳書に『クルーグマン教授の経済入門』(ちくま学芸文庫)、バロウズ著『ソフトマシーン』(河出文庫)、共訳にピケティ著『21世紀の資本』(みすず書房)など。
文筆家、俳人。パリ第4大学博士課程修了。著書に『青ひげ夫人と秘密の部屋』(光文社)、『人はなぜ物語を求めるのか』(ちくまプリマー新書)など。訳書にトマス・パヴェル『小説列伝』(水声社)。