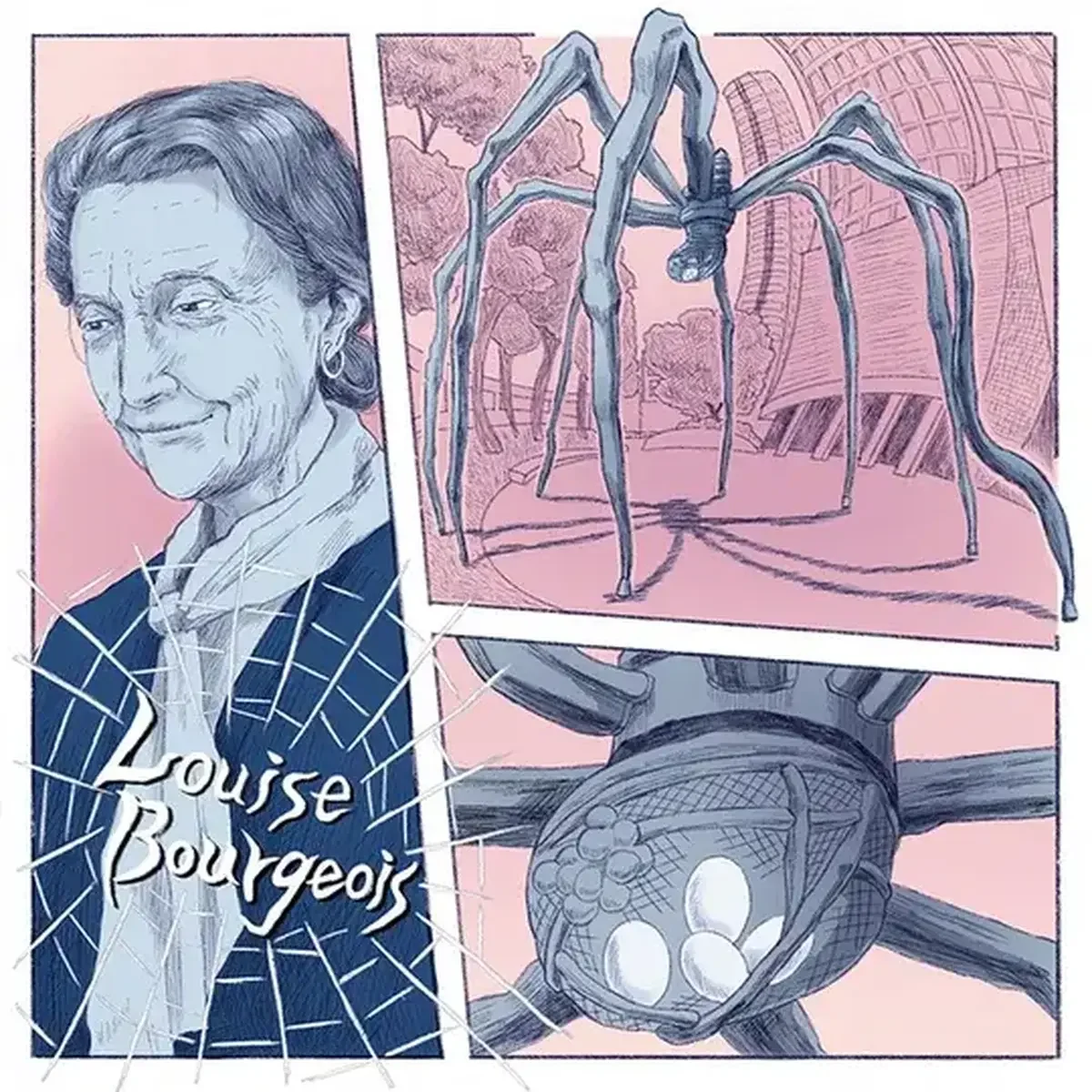「死者」の感覚を味わってみませんか?

幽霊になってみたいと思いませんか? 特別な知識も技術もいりません。ただ一歩、ある作品に足を踏み入れるだけで、この世ならざるものになれるのです。
アルゼンチン出身の現代美術家、レアンドロ・エルリッヒ。教室や美容院といった日常空間を舞台装置のように組み立て、その中に「ずれ」を仕掛けることで、人々の感覚を揺さぶってきました。代表作のひとつが、金沢21世紀美術館に恒久展示された《スイミング・プール》。ありふれたプールをモチーフにしながら、いまや美術館を象徴する存在となっています。
プールサイドに立ち、青い水面を覗き込むと、水中には人がいます。しかし奇妙なことに、その人々は地上と変わらぬ身振りで立ち、こちらに手を振っているのです。仕掛けは単純で、水は強化ガラスの上にわずか10センチ張られているだけ。その下に広がる青い地下空間へは、館内の通路を抜けて入り込むことができます。
この作品はしばしば、きらめく水面の美しさや建築的な意外性で語られます。けれど、しばらく佇んでいると、別の感覚が忍び寄ってきます。プールの底に見える人影は「死者」なのではないか。生者は水中で呼吸できず、悠々と歩くことなどありえないのだから。水の底からこちらに手を振る姿は、この世の摂理から外れた存在にほかなりません。不思議なことに、私たちはそれを恐れるどころか、むしろ自らも水の底に下りたいと望んでしまう。地下通路を抜け、青い光に満ちた空間から水面を仰いだとき、私たちも死者の側に立っているのです。
エルリッヒの作品の多くは、見る人がいてこそ成立します。ひとたび足を踏み入れれば、私たちは鑑賞者ではなく、作品を支える演者となるのです。そこで待ち受けるのは、日常に見えて日常でない光景──たとえば鏡に映らぬ自分や、重力から解き放たれた身体です。日常の摂理から切り離された瞬間、私たちは悟ります。自分はもう、この世の側にはいないのだと。幽霊になるとは、きっとこういう感覚なのでしょう。
さあ、この週末は、美術館で幽霊になってみませんか。
東海大学教養学部芸術学科准教授。専門は現代美術史、装飾史。研究のほか、イラストやデザインなどでも幅広く活躍中。近著に『いとをかしき20世紀美術』(亜紀書房)ほか。